ベトナムでオフショア開発のメリットやデメリット | Hachinet Software
オフショア開発というと、一般的に「安価」というコストメリットをイメージされる方が多いかと思います。しかし、近年ではその様相に変化がみられています。様々な要因がありますが、一例としてベトナム国内の経済成長や、日本をはじめとするグローバルでのIT人材に対する需給バランスの変動などにより、コストメリットは以前に比べ相対的に縮小傾向にあります。近年ではむしろ、ITに関連するマーケットの拡大とリソースの不足によって、リソース面でのメリットに対する注目が高まっています。
2021年11月26日

オフショア開発というと、一般的に「安価」というコストメリットをイメージされる方が多いかと思います。しかし、近年ではその様相に変化がみられています。様々な要因がありますが、一例としてベトナム国内の経済成長や、日本をはじめとするグローバルでのIT人材に対する需給バランスの変動などにより、コストメリットは以前に比べ相対的に縮小傾向にあります。近年ではむしろ、ITに関連するマーケットの拡大とリソースの不足によって、リソース面でのメリットに対する注目が高まっています。
1. はじめに
オフショア開発というと、一般的に「安価」というコストメリットをイメージされる方が多いかと思います。しかし、近年ではその様相に変化がみられています。様々な要因がありますが、一例としてベトナム国内の経済成長や、日本をはじめとするグローバルでのIT人材に対する需給バランスの変動などにより、コストメリットは以前に比べ相対的に縮小傾向にあります。近年ではむしろ、ITに関連するマーケットの拡大とリソースの不足によって、リソース面でのメリットに対する注目が高まっています。
一方で、オフショア開発の活用には主に文化的、地理的な隔たりに起因するコミュニケーション等における課題やリスクが存在していることは無視できません。
ゆえに優特徴だけでなく、デメリットやリスクも含めて認識をしたうえで、適切に対応をすることではじめてそのメリットを十二分に活かした運用が実現できると考えます。
こちらの記事がベトナムでのオフショア開発における特徴・リスクに対する理解を深める一助となり、最適なソリューションの検討に役立てていただけますと幸いです。
2. オフショア先にベトナムが多く選ばれる理由
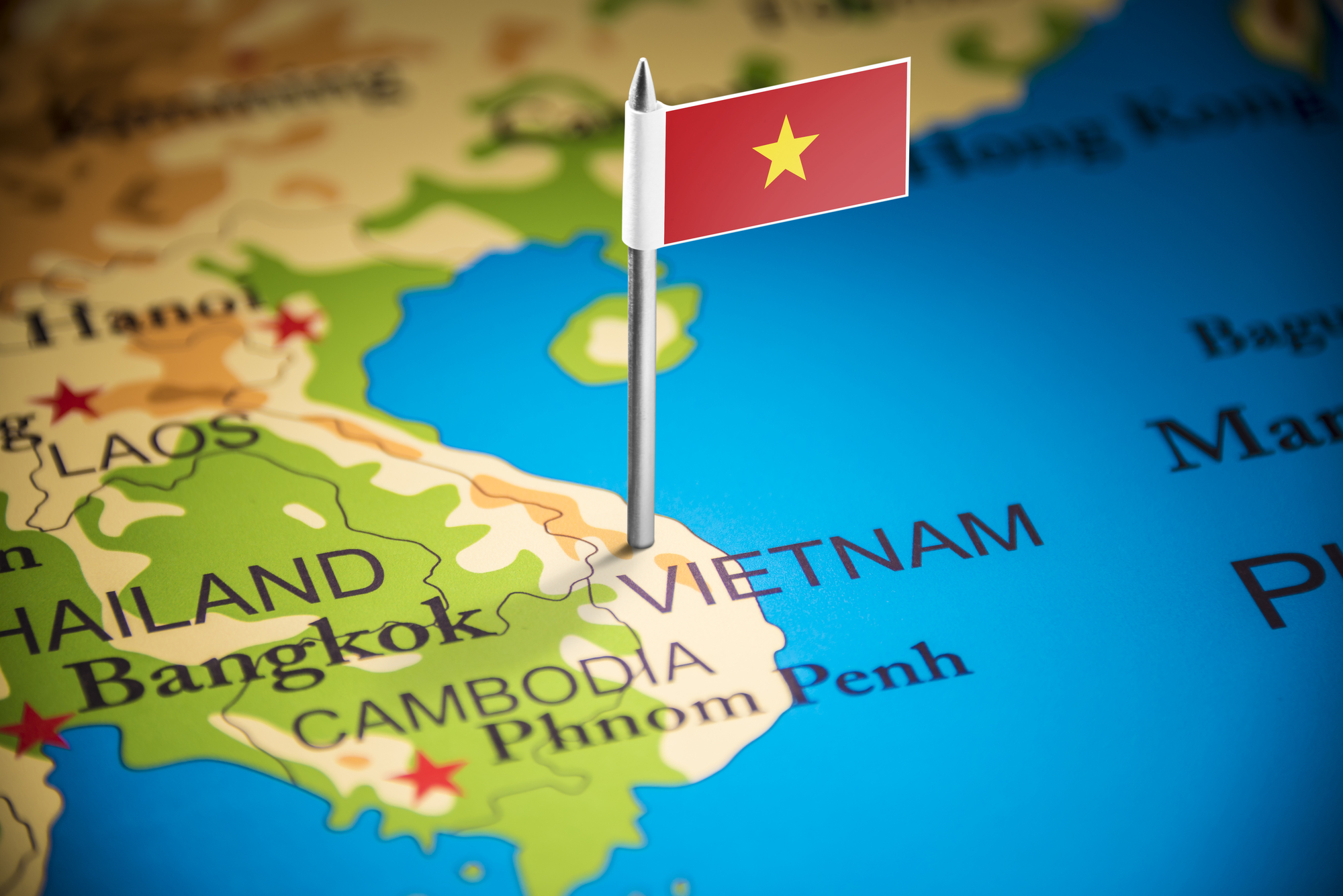
◇親日的な国である点
1点目に上げられるのが、親日的な国である点です。海外でビジネスを行う上で、親日的な国であるということは、非常に重要です。反日の傾向がある国では、トラブルが発生するリスクを考えなければならないためです。
ベトナムは日本に対して好印象を持っている国ですので、友好なコミュニケーションをとりながらビジネスをすすめることができます。また、ベトナム人は勤勉で真面目であるといわれており、日本人と国民性が似ている点もビジネスパートナーとして選ばれる理由です。
また、ベトナムの学校教育で日本語教育に力を入れている学校が多く、日本へ留学する学生も多くいることから、日本語を理解できる若者が多く存在することもメリットです。
◇コスト
急速な経済成長を遂げているベトナムですが、依然として日本国内に比べると大幅なコストや税金のメリットを享受できる環境にあります。具体的な単価については、オフショア開発会社によっても差が出てきており、二極化が進みつつありますが、概ね1/4から1/3程度の単価と言われています。
さらに、単価と同様に、オフショア開発企業によって品質にも大きなばらつきが見られるようになってきていますが、特徴①でもご紹介した通り全体的な水準として開発力は年々上昇傾向にあります。
そのため、単価をある程度抑えつつスキルの高いエンジニアを活用した開発環境が構築しやすいという、優れたコストパフォーマンスを期待することが可能です。しかしながら、長期間的にはこのコスト特徴は縮小していく可能性が非常に高いことから、価格だけに着目してベトナムでのオフショア開発を検討するのはリスクがあるかもしれません。
◇豊富かつ優秀なエンジニアリソース
ベトナムでは国策として高度IT人材の輩出を掲げており、優秀な理系大学出身のIT人材が安定的に市場に供給されています。
その数は年々増加を続けており、毎年4万人の学生が専門的なITの教育課程を終え、2021年度には国内のITエンジニアの総数が約35万人に達すると言われています。
さらに、ベトナムではITエンジニアはいわゆる花形の職業の一つと認識されており、高い給与・人気から優秀な人材がこぞってIT業界を目指すという背景があります。
例えば、ベトナムでは大手IT企業が自ら大学を設立し、そこでエンジニアを学生の若手年代から育成をIT企業自ら行っています。そ中には、大学と連携して、教育を行っているようなオフショア開発企業さえもあります。そういった企業の教育で技術を養った卒業生が新しいオフショア開発企業を起業することも多く、自らの経験をもとに自身の企業でも教育制度が整える企業が多い傾向があります。
一方日本に目を向けると、周知のとおり労働人口自体が減少傾向にあり、特に若いIT人材の確保が年々難しくなっている状況です。経済産業省によれば、2030年には約40~45万人ものIT人材が不足すると見られています。こうした状況から、優秀なエンジニアを豊富に確保できるということは、日本の組織にとって非常に大きなメリットといえるでしょう。
特に大規模プロジェクトにおいては、日本国内では受託先が限られる一方で、ベトナムでは豊富なリソースを背景に比較的受け入れやすい環境にあります。管理面での難しさといった課題はあるものの、大規模プロジェクトの場合は主なメリットの1つであるコストメリットも非常に大きくなることから、検討の価値は非常に高いと思われます。
◇多様な条件の開発に対応しやすい
労働力が豊かな国に業務委託することで、大量に人材を確保可能です。そのため、短納期の開発や大規模な開発など、多様な条件の開発に対応可能です。
変化の激しいグローバル市場を見据え、スピーディーな開発体制を構築することもできます。求められるシステムを迅速に用意できるのは大きな強みです。
3. オフショア開発の課題・問題点
◇コミュニケーションが取りづらいことがある
委託先が外国である関係上、コミュニケーションの問題は免れません。仕様書や情報共有などの翻訳に手間取ることがあります。そのため、委託先側は日本語に対応している担当者がいない場合、英語もしくは現地の母国語を解する方スタッフが必要です。
現在、インターネットが普及し、コミュニケーションの手段自体は豊富ですのに、会議の際は時差の問題を考慮しなければなりません。特に緊急時などは、迅速な連絡・対応依頼が難しい場合があります。
◇文化の違いから、認識の差が生じやすい
委託先の国と日本では、文化にさまざまな違いがあります。価値観やビジネスマナー、仕事観等の違いも少なくありません。この違いからトラブルが起こることが考えられます。
例として、一般的に海外では契約にない業務は行われません。要件定義をしっかりしておかないと、発注側にとって品質が低いと感じる成果物になるリスクがあります。
4. オフショア開発を失敗しないための対策
◇コミュニケーション文化の違いを理解する
グローバルで展開するビジネスを考える時の基本となるのが、日本はハイコンクエストのコミュニケーションをとれる国であるという認識です。日本は単一民族の国なので、会話などのコミュニケーションにおいて、同一民族であれば当然わかるであろう部分においては、曖昧な表現をすることがよくみられます。こうした曖昧な表現が通用することをハイコンクエストと呼びます。
一方でグローバルな視点で考えると海外の国の多くは多様性のある多民族国家です。こうした国では日本で通用しているハイコンクエストのコミュニケーションは通用しません。他民族国家では文化的な共有部分が希薄なため、全ての項目について曖昧ではなく明確に表現し説明していかなければなりません。このような社会をローコンクエストと呼びます。
海外の国と取引をするオフショア開発では、ハイコンクエストでなければ通用しない曖昧な部分は無くし、ローコンクエストでのコミュニケーションを徹底する必要があります。また、資料なども徹底してローコンクエストで作成しましょう。「これ」「この」などの指示語は極力使用せず、明確な用語で説明しましょう。
◇オフショア先でテストチームを発足する
オフショア先でテストチームを発足するのも解決策のひとつです。上流工程からテストチームを参画させることで、案件とのズレを早期に発見できます。
また、テスターと開発者が同じ母国語なので密なコミュニケーションが取りやすく、開発状況が把握しやすくなり、その結果日本側で管理がしやすくなります。
◇ソースコードのレビュー
開発状況を把握するにはソースコードのレビューは非常に重要です。オフショア側に開発を丸投げすることはお勧めできません。丸投げすると、ユーザーテストの段階で認識違いが頻出し不具合が多く発生するケースや、リリースはできたものの拡張性がなく追加開発がしにくくなるケースが考えられます。
◇密なコミュニケーションを取る
前述のローコンクエストのコミュニケーションを取ると同時に、密なコミュニケーションを取るように積極的に取り組みましょう。具体的にはコミュニケーションツールで密なやり取りや図などを用いたコミュニケーション、場合によっては画面共有しながらのビデオ会議など、開発状況を把握することが重要です。また、日本とオフショア先の橋渡しの存在となるブリッジSEを現地に置くことも重要になってきます。
5. 結論
本記事がベトナムにおけるオフショア開発を検討される上で少しでも参考になれば幸いです。私たちHachinetはオフショアにおける品質保証に加え、品質を重視したオフショア開発にも取り組んでいます。オフショア開発やシステム開発に関してお悩みなどございましたら、ぜひHachinetにお気軽にお問い合わせください。御社のオフショアプロジェクトを最大限にサポートさせていただきます。
ITエンジニア派遣をご検討されている方々はぜひ一度ご相談ください。
※以下通り弊社の連絡先
アカウントマネージャー: クアン(日本語・英語対応可)
電話番号: (+84)2462 900 388
お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。
- オフショア開発
- エンジニア人材派遣
- ラボ開発
- ソフトウェアテスト
電話番号: (+84)2462 900 388
メール: contact@hachinet.com
お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。
無料見積もりはこちらから
Tags
ご質問がある場合、またはハチネットに協力する場合
こちらに情報を残してください。折り返しご連絡いたします。
関連記事

現場レベルで解剖するDartの実力:大規模プロダクトはどう設計し、どこで壁に当たったのか
Dart 入門の情報は多いものの、「数百万ユーザー規模でどう動いているのか」まで踏み込んだ解説は多くありません。本記事では、有名プロダクトにおける実装構造・移行戦略・スケール時の問題点まで掘り下げます。目的は表面的な導入事例紹介ではなく、再現可能な技術的知見を整理することです。
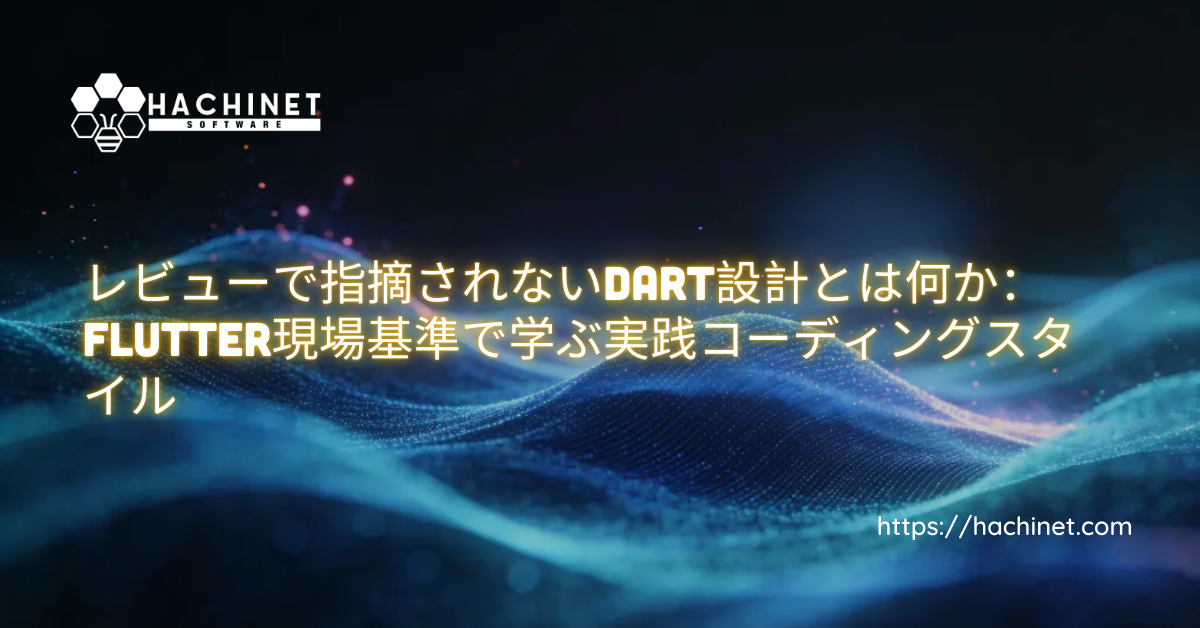
レビューで指摘されないDart設計とは何か:Flutter現場基準で学ぶ実践コーディングスタイル
Dart 入門で文法を学び、Flutterで画面を作れるようになると、多くの開発者が「それなりに動くアプリ」を作れるようになります。しかし実務では、それでは不十分です。レビューで問われるのは、可読性、変更耐性、責務分離、そしてチーム全体で維持できる一貫性です。本記事では、Flutterプロジェクトで実際に評価されるDartコーディングスタイルを、抽象論ではなく具体基準として掘り下げます。
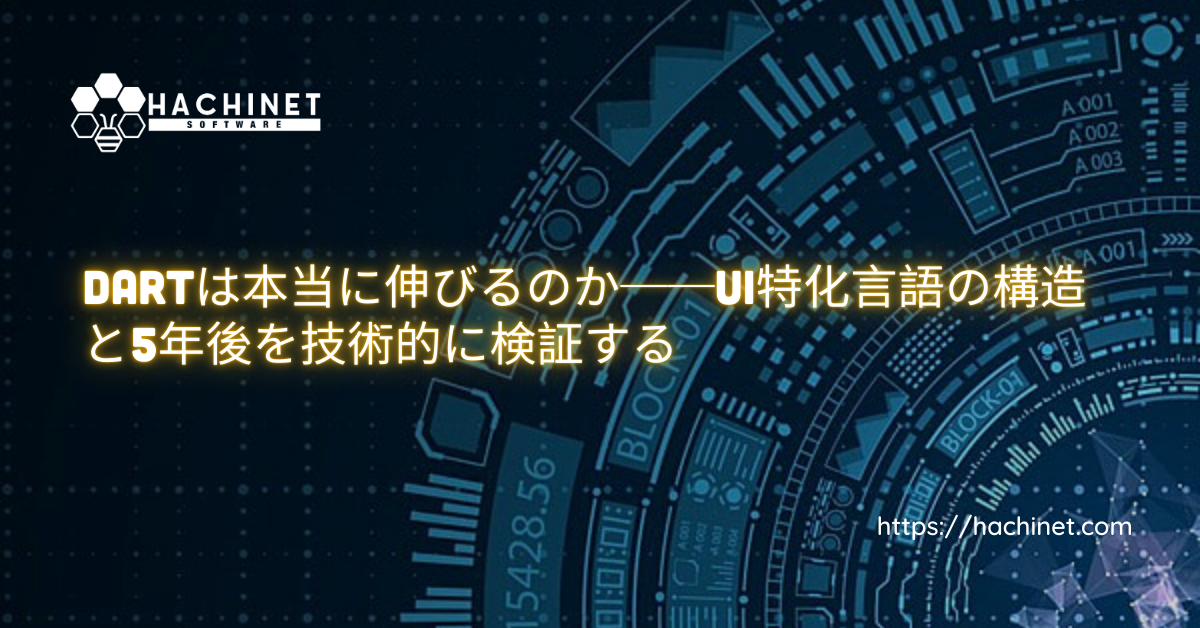
Dartは本当に伸びるのか──UI特化言語の構造と5年後を技術的に検証する
Dartは巨大言語ではありません。それでも一定の存在感を維持しているのは、設計思想が一貫しているからです。Dart 入門を検索する人の多くはFlutter開発を前提にしているはずです。本記事では、感覚的な「将来性がありそう」という議論ではなく、言語設計・市場構造・採用実態を踏まえ、Dartが今後5年でどの位置に収まるのかを技術視点で具体的に検証します。
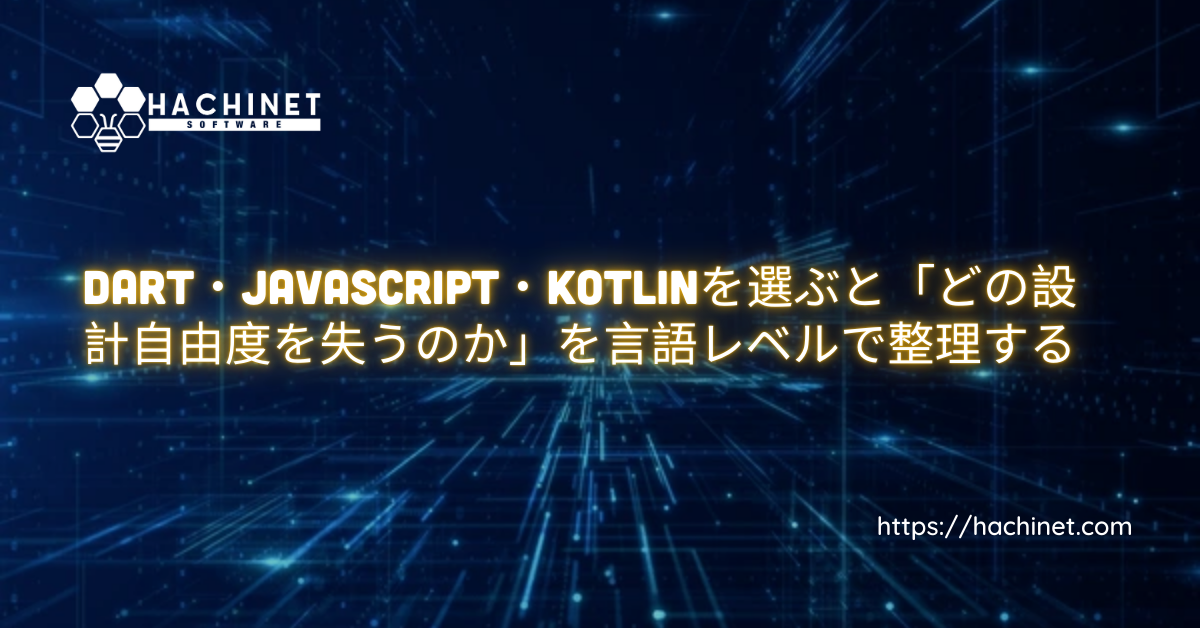
Dart・JavaScript・Kotlinを選ぶと「どの設計自由度を失うのか」を言語レベルで整理する
Dart 入門と検索している時点で、多くの人はまだ「言語」を選んでいるつもりでいます。 しかし実務では、言語選定とは設計の自由度をどこまで手放すかの契約です。 Dart・JavaScript・Kotlinは、用途が違うのではなく、破壊する設計レイヤーが根本的に違う。この記事では、その違いをコードや流行ではなく、アーキテクチャの不可逆点から整理します。

Dartの文法は偶然ではない|基礎構文から読み解く設計思想
Dartは「書けば動く」言語ではありません。代わりに「考えずに書くことを許さない」言語です。本記事では文法を並べるのではなく、Dartがどのような失敗を事前に潰そうとしているのかを軸に解説します。ここを理解すれば、Dartの構文は自然に腑に落ちます。

Dartはなぜ「書かされている感」が強いのか──Flutter・Web・Serverに共通する設計拘束の正体
Web Dart 入門としてDartに触れた多くの人が、「書けるが、自分で設計している感じがしない」という感覚を持ちます。サンプル通りに書けば動く、しかし少し構造を変えた瞬間に全体が崩れる。この現象は学習者の理解不足ではなく、Dartという言語が設計段階で強い制約を内包していることに起因します。本記事では、Dartがどのようにコードの形を縛り、なぜその縛りがFlutter・Web・Serverすべてで同じ問題を引き起こすのかを、実装視点で掘り下げます。
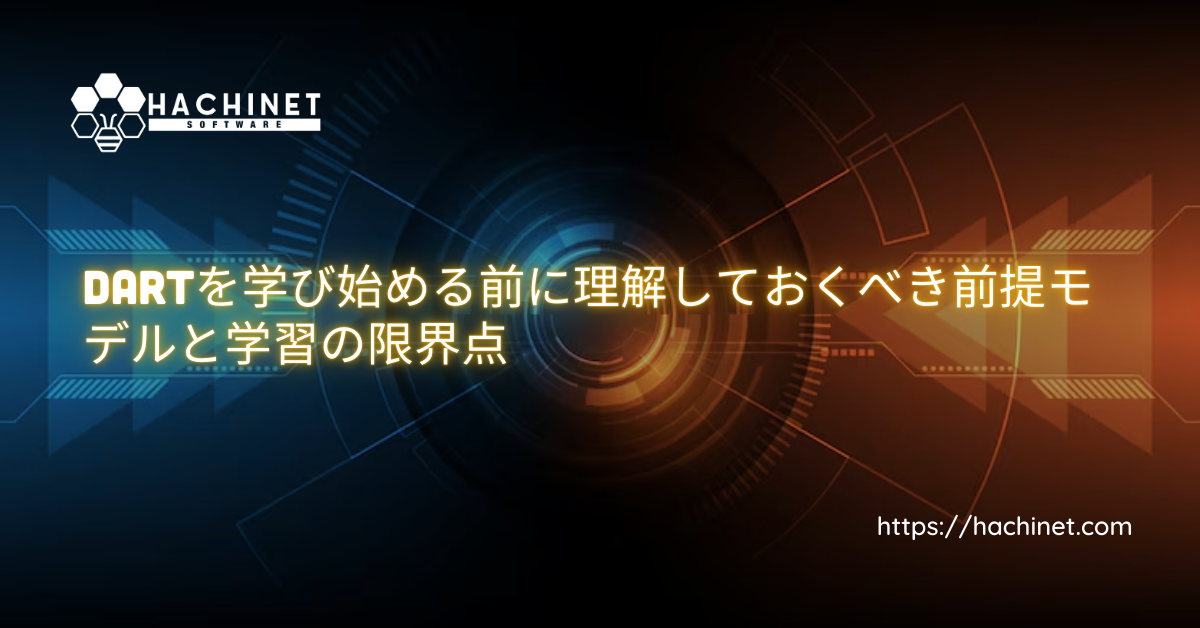
Dartを学び始める前に理解しておくべき前提モデルと学習の限界点
「Dart 入門」という言葉は、Dartが初心者でも気軽に扱える言語であるかのような印象を与えますが、実際のDartは、現代的なアプリケーション開発で前提とされるプログラミングモデルを理解していることを前提に設計された言語です。文法自体は比較的素直であっても、状態管理、非同期処理、型による制約といった考え方を理解しないまま学習を進めると、「動くが理由が分からないコード」が増え、小さな変更で全体が破綻する段階に必ず到達します。本記事では、Dart学習で頻発するつまずきを起点に、学習前にどのレベルの理解が求められるのかを、曖昧な励ましや精神論を排して整理します。
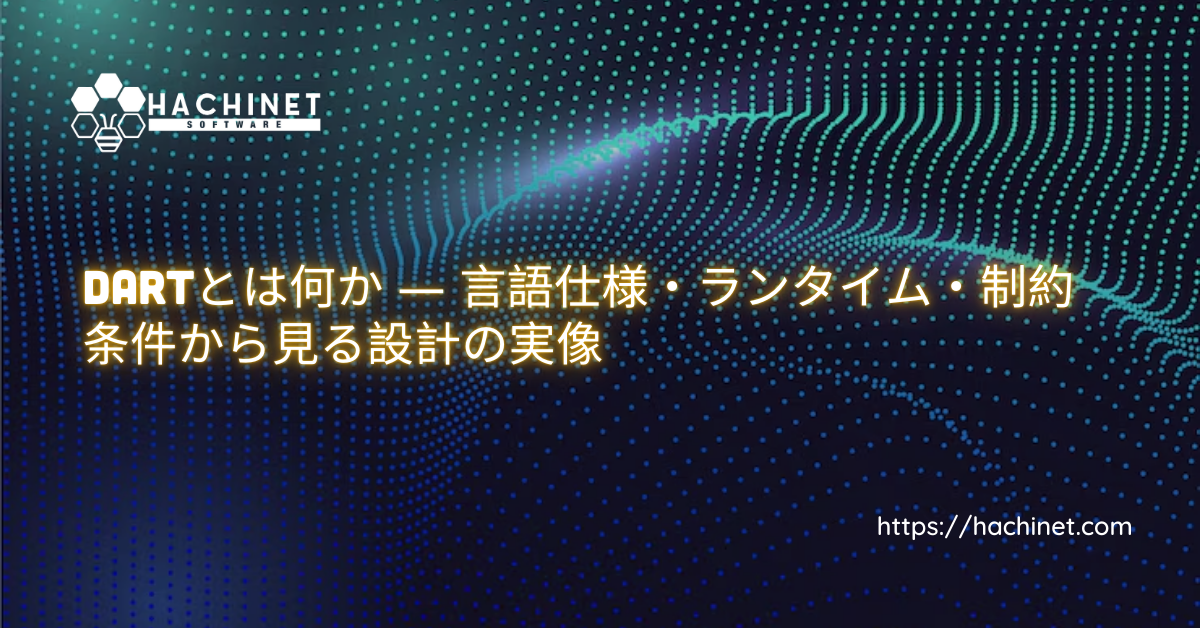
Dartとは何か ― 言語仕様・ランタイム・制約条件から見る設計の実像
Dart 入門や Dartとは というキーワードで語られる内容の多くは、表層的な機能説明に留まっています。しかしDartは、流行に合わせて作られた軽量言語ではなく、明確な制約条件を起点に設計された結果として現在の形に落ち着いた言語です。本記事では、Dartを仕様・ランタイム・設計判断の連鎖として捉え、その必然性を整理します。
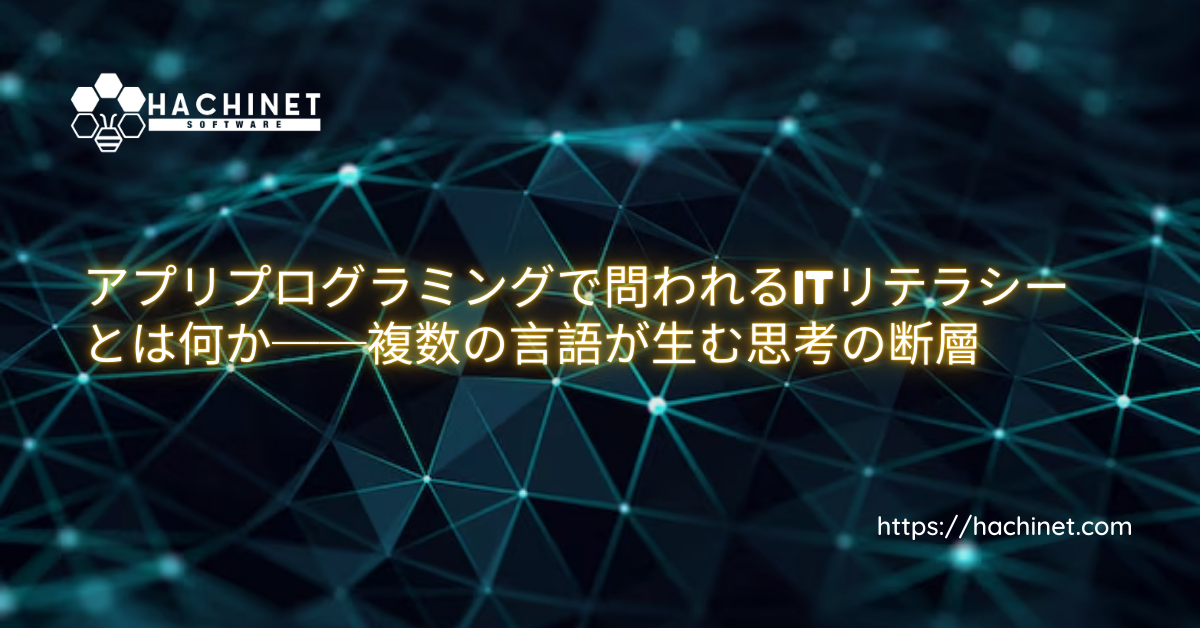
アプリプログラミングで問われるITリテラシーとは何か──複数の言語が生む思考の断層
ITリテラシーがあるかどうかは、プログラミング言語を知っているかでは決まりません。本質は、なぜアプリプログラミングが複数の言語に分かれているのかを、構造として理解しているかです。この記事では、言語ごとに異なる役割と思考モデルを明確にし、非エンジニアが判断を誤る理由を技術構造から説明します。
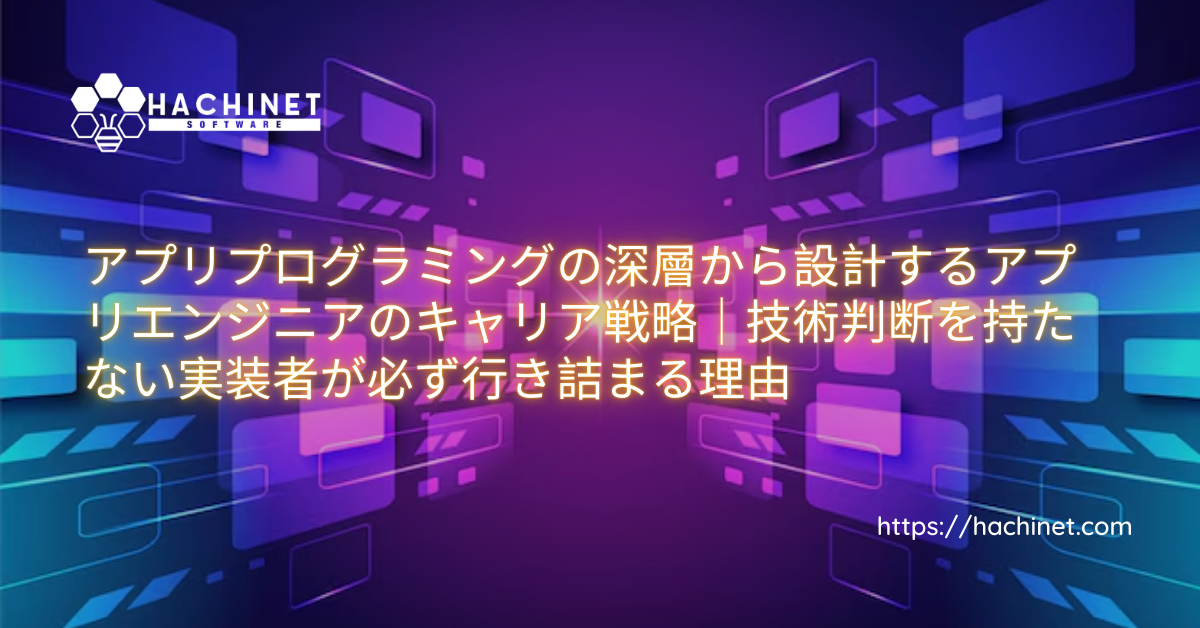
アプリプログラミングの深層から設計するアプリエンジニアのキャリア戦略|技術判断を持たない実装者が必ず行き詰まる理由
アプリプログラミングの経験年数が増えても、技術者としての評価が上がらないケースは珍しくありません。その多くは、アプリ開発を「作る仕事」として捉え続けていることに起因します。アプリエンジニアのキャリア戦略を考えるうえで重要なのは、実装スキルではなく、技術的な判断をどこまで担ってきたかです。本記事では、アプリプログラミングの深層にある設計・判断の観点から、キャリア形成の実態を整理します。
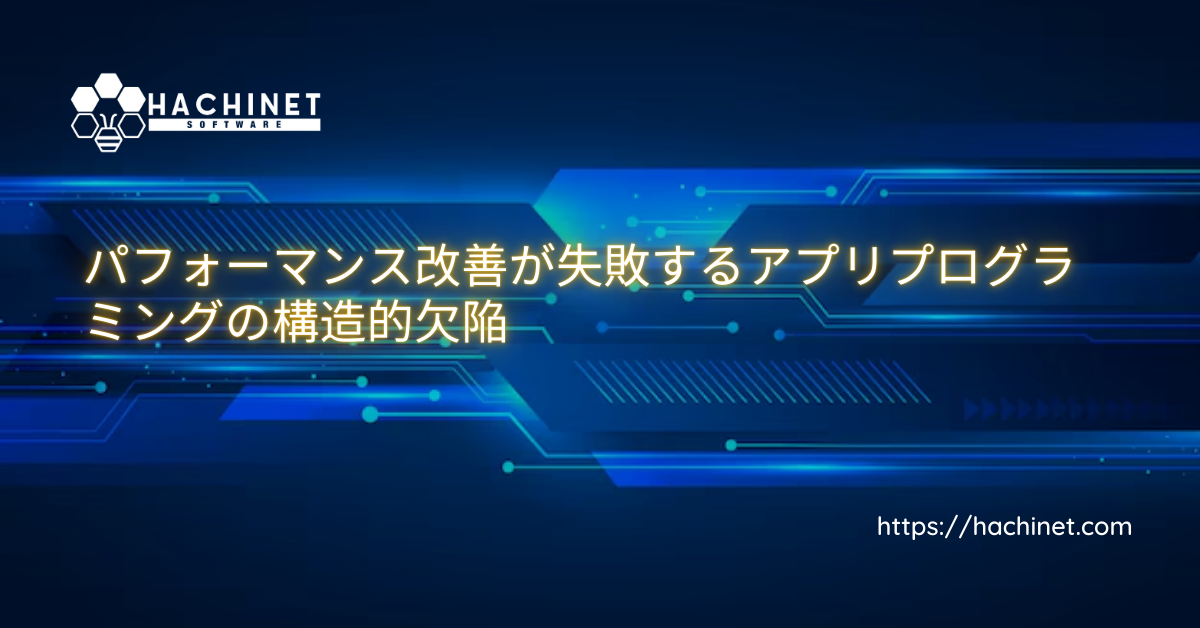
パフォーマンス改善が失敗するアプリプログラミングの構造的欠陥
アプリが重くなるとき、表に出るのはスクロールのカクつきや起動遅延だ。しかしユーザーが離脱する原因は、その「見えている遅さ」ではない。アプリプログラミングの内部で、処理順序・責務分離・実行単位が崩れ始めていることに、誰も気づいていない点にある。





