【2022版】オフショア開発の現状や動向 | Hachinet Software
将来的には、デジタルやITの分野で人材育成に取り組むという情報があります。また、100円ショップはビッグデータを活用した注文システムで高い利益率を生み出しています。多くのデジタル化過程は、ECサイトの構築や配送場所の構築など、身近な場所でも新しいビジネス形態を生み出しています。
2021年08月24日

将来的には、デジタルやITの分野で人材育成に取り組むという情報があります。また、100円ショップはビッグデータを活用した注文システムで高い利益率を生み出しています。多くのデジタル化過程は、ECサイトの構築や配送場所の構築など、身近な場所でも新しいビジネス形態を生み出しています。
1. コロナ禍の経済状況
1.1 日本の企業の状況
コロナの影響が長引くにつれ、輸出増加の影響を受けた産業と、移動制限や労働時間の短縮の影響を受けた産業との格差が明らかになりました。一部の企業は悲しい業績を上げています。
鉄道については、JR東日本の最終損失は5,779億円でした。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを運営する会社も、541億円の最終損失を発表しました。日本航空(ANA)も4,046億円の過去最高の赤字を発表しました。
1.2 新ビジネスタイル
2021年7月に資生堂は大手化粧品メーカーであり、主な顧問としてAccentureと合弁会社を設立されました。新会社は資生堂にデジタル・情報技術関連のサービスや商品を提供することを目指しています。
Accentureとの連携により、資生堂は消費者や市場の急速な変化に対応できます。 さらに、デジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation)を加速し、デジタル中心のビジネスモデル(Business Model)を革新し、日本で世界標準のIT下部構造と運用を構築します。
将来的には、デジタルやITの分野で人材育成に取り組むという情報があります。また、100円ショップはビッグデータを活用した注文システムで高い利益率を生み出しています。多くのデジタル化過程は、ECサイトの構築や配送場所の構築など、身近な場所でも新しいビジネス形態を生み出しています。
いずれの場合も、値の変化または継続的な変化に対応できる為に、経験に基づいてITシステムを構築して使用しようとしています。
2. 発生する問題
2.1 人材不足
ITエンジニアは、人材が深刻に不足しているため、現在、採用するのが最も難しい仕事です。
将来、退職したエンジニアの数は新入社員の数を上回り、エンジニアの人口は減少します。
また、IT技術の需要は今後も拡大が見込まれており、深刻な人材不足が発生しています。
最新の技術は絶えず変化する分野です。ですから、現在人材はIT技術の急速な発展に追いついていません。
『2015問題』70%はITエンジニア不足割合です。1191人の中800人以上のITスタッフが、システムの開発、運用、保守中に労力が不足について問題が発生することを懸念しています。
最近、全てデジタルで管理され、情報が保護されます。そのため、情報保護に携わるエンジニアの需要が高まっています。(日経新聞によると)
2.2 エンジニアの品質は保証されておらず、職場環境が悪化する可能性がある
厳しいと指摘されるIT職場ですが、最近、職場環境の改善に熱心な会社が増えています。
あの調査では、「今後2~3年、あなたの仕事の負荷はどのようになると予測しますか」について聞きました。合計70%の回答者が、業務負荷が増えると予想します。
また、「あなたが所属する組織は、人手不足を補うための対策を打っていますか」と聞いたところ、「対策を打っていない」と回答比率が68.3%であります。
ユーザー企業のシステム部門については、「対策を打っていない」と80.6%でした。次、64.0%がITベンダーでした。ユーザー企業はITベンダーよりも2015年の問題を認識していないようです。(日経新聞によると)
3. オフショア開発の利点をどう活用するか?
3.1. 委託開発の利点
委託される内容を見ると、今まで最も人気のあった開発は、Webシステム開発とスマートフォンアプリケーション(Smartphone Application)開発でした。
特に、社会情勢の変化・コロナ災害、在宅勤務の増加、レストランでの販売制限により、ECサイトやWebサービス開発などのアプリケーション開発が進んでいます。
多くの企業がこの分野で非常に優れています。その中に、Hachinet Softwareであり、評判の良いWebサイト「https://www.offshore-kaihatsu.com/」でTOP 3のオフショア企業にランクされています。
一方、昨年頃からオフショア開発と同じくらい重要なシステムを開発したいプロジェクトが増えています。一般に、重要なシステムは大規模で広範囲をカバーするため、豊富な経験が必要です。
以前、ほとんどの開発は日本で行われていました。 しかし、日本ではIT技術者が不足しているため、オフショア開発が増えています。
企業のショアア開発も近年規模が拡大しており、ミッションクリティカルなシステムの開発に対応できる企業もあります。 インドを含むベトナム企業は、コアシステムに取り組み始めています。
また、企業のショアア開発も近年規模が拡大しており、重要なシステムの開発に対応できる企業もあります。 インドを含むベトナム企業は、コアシステム(Core System)に取り組み始めています。
3.2. 将来の新しい活用術
外国企業の特徴の一つは、世界中の最新のソフトウェア技術を取り入れています。主に米国を中心にあります。 発想を持っているのは、できるだけ早く良いものを取り入れることです。
そのため、さまざまな分野の新しいビジネスマーナを観察と聴取し、それらを組み合わせています。
そういう意味では、技術やビジネスの背景で日本をリードしている場合が多いようです。
これを活用するためには、これまでのように外国の開発会社に外注するだけでなく、外国の会社に相談して共同開発することも重要です。
さらに、外国の開発会社は、AI開発やブロックチェーン(Blockchain)開発などの最新技術を備えたシステムに優れている可能性があります。 特にベトナムでは、多くのAIエンジニアが訓練を受けており、さまざまなシステムで使用できます。
オフショア開発を通じて最新の技術と最新のビジネスプラットフォームを組み合わせることは、将来に活用する方法と使用されています。
4. Hachinetのオフショアサービス
4.1 Hachinetの概要
日本をはじめとする先進国の多くが抱えている問題の1つが、少子 高齢化です。特に日本はその傾向が強く出ており、子供が少ない というだけでなく若手の労働人口自体も少なくなってきています。 その反面、約9000万人の人口を誇るベトナムは若い力に溢れ、年代 別人口では20代がトップであり、中長期でみてもIT人材の確保先 として有望視されています。
IT業界の特徴は、進度どおりの完了、タイムリーで高速な処理です。Hachinetでは、IT業界の絶えない変化に常に対応し、それに追いつくために、能力開発の問題を重んじています。
詳細はこちらをご覧下さい。
4.2 Hachinetのサービス
Hachinetは、お客様にもっと多くの選択と質の高いサービスを提供することを目標として努めています。当社は常に技術的な専門知識と優秀な人材を向上させ続けています。
現在、Hachinet Softwareで様々なサービス発達しています。
- ビジネスシステムプリケーション
- Website開発
- フロントエンドアウトソース開発
- モバイル開発 , アプリ開発
- ジャワシステム開発
- .NETシステム開発
- Cobolシステム
- みなさまから信頼される 「総合人材サービス」
詳細はこちらをご覧下さい。
関連記事:【offshore-kaihatsu.com】で100社の優良オフショア開発企業一覧2位を獲得したHachinet Software
5. 結論
弊社では専門的にITオフショア開発を中心で事業を行っております。
弊社が対応するサービスは下記となります。
① ウエブアプリケーション(.NET , JAVA, PHP,..)
➂ モバイルアプリケーション: IOS (Swift, Object C), Android (Kotlin, Android)
④ システム構築 (Cobol , ERP ...)
⑤ DXソリューション
⑥ 新技術 (Blockchain ...)
ベトナムでオフショア開発取引先をお探しの場合は、弊社ハチネットでは完全な企業メカニズムシステム、多様な開発言語、Devworkシステムは豊富な人材を採用、ベトナムのオフショア開発におけるトップ10企業の1つです。
現在、Hachinet Softwareの顧客は八割日本企業です。弊社のエンジニアは、技術系の豊富な知識だけでなく、専門的な日本語で日本客とやり取りして、お互いの目的を達成します。お客様に届けた書類・ドキュメントは全部日本語で対応・提供します。
Hachinetでは、常にソフトウェアの品質と顧客の満足度を重視しています。弊社のサービスをご利用になるお客様には、品質をはじめ、責任もちゃんと持っております。計画段階から保守まで、さまざまな工程を正確に実地して、納品期間を守ると保証しております。
弊社のサービスにご興味がございましたら、こちらのメールアドレスにご連絡お願いします。ご連絡をお待ちしております。
オフショア開発でERPシステムをご検討されている方々はぜひ一度ご相談ください。
※以下通り弊社の連絡先
アカウントマネージャー: クアン(日本語・英語対応可)
電話番号: (+84)2462 900 388
メール: konnichiwa@hachinet.jp
お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。
- オフショア開発
- エンジニア人材派遣
- ラボ開発
- ソフトウェアテスト
電話番号: (+84)2462 900 388
メール: contact@hachinet.com
お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。
無料見積もりはこちらから
Tags
ご質問がある場合、またはハチネットに協力する場合
こちらに情報を残してください。折り返しご連絡いたします。
関連記事

Dartは本当に就職に強いのか?Flutter求人の構造・年収帯・生存戦略まで踏み込んで解説
Dart入門と検索する段階で、多くの人はすでに疑問を持っています。「学びやすいらしいが、それで就職できるのか」。結論を先に言えば、Dartは単体では市場価値を持ちません。評価対象はあくまで Flutter です。本記事では、日本・ベトナム・欧米市場の採用構造を具体的に分解し、年収レンジ感やスキル要件まで踏み込んで現実的に整理します。

Flutterで頭打ちになる人が見落としているDart基礎設計の決定的差
Flutterは学習初期の成功体験が早い技術です。しかし半年後、コードが肥大化し、再利用できず、状態管理が複雑になり、自分でも触りたくないプロジェクトになるケースは少なくありません。その分岐点はDart理解の深さです。Dart 入門レベルの文法理解で止まり、言語仕様や実行モデルに踏み込まなかった人ほど設計が破綻します。本記事では「なぜDart理解が不足するとFlutter開発が不安定になるのか」を技術構造レベルで解説します。

Dartのオブジェクト指向は「設計しない」ことで成立している
Dartのオブジェクト指向は、学習段階では拍子抜けするほど単純です。しかし実務で数万行規模になると、多くの言語で起きる「設計崩壊」が、Dartでは驚くほど起きにくい。本記事では、その理由を「美しい設計論」ではなく、どこで壊れ、どこで踏みとどまるのかという実装結果ベースで掘り下げます。
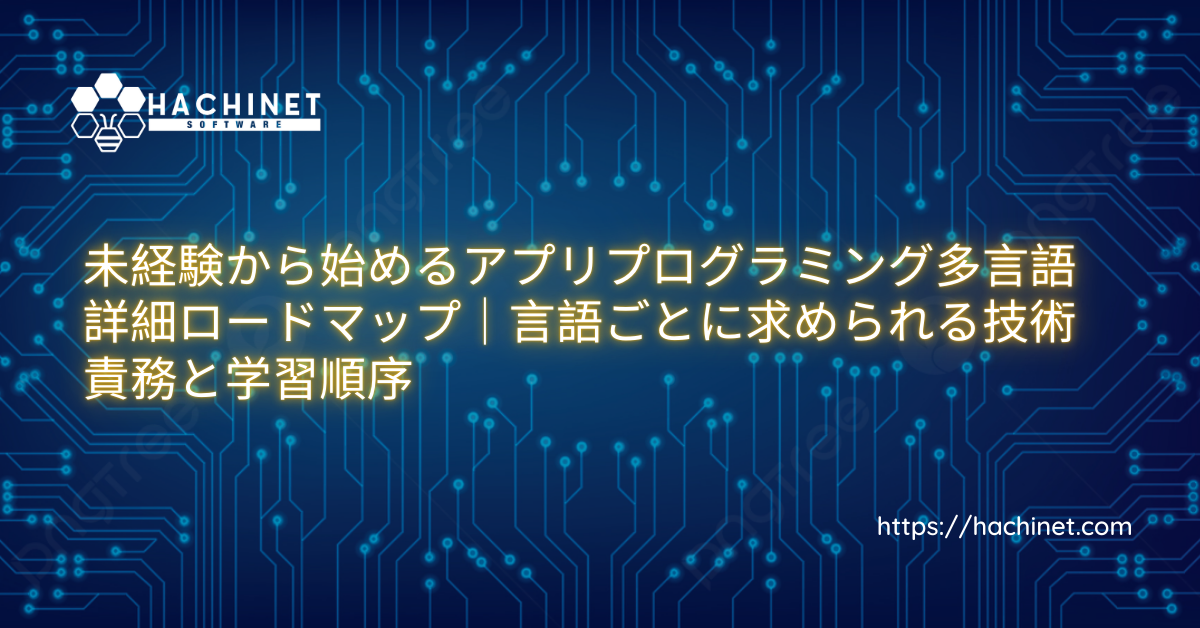
未経験から始めるアプリプログラミング多言語詳細ロードマップ|言語ごとに求められる技術責務と学習順序
未経験からアプリプログラミングを学ぶ際、多くの人は「どの言語を覚えればアプリが作れるか」という問いを立てます。しかし実務では、アプリは単一言語で完結することはなく、複数の言語が異なる責務を分担する構造体として存在します。本記事では、言語を単なるスキルではなく、アプリを成立させるための必須構成要素として整理します。
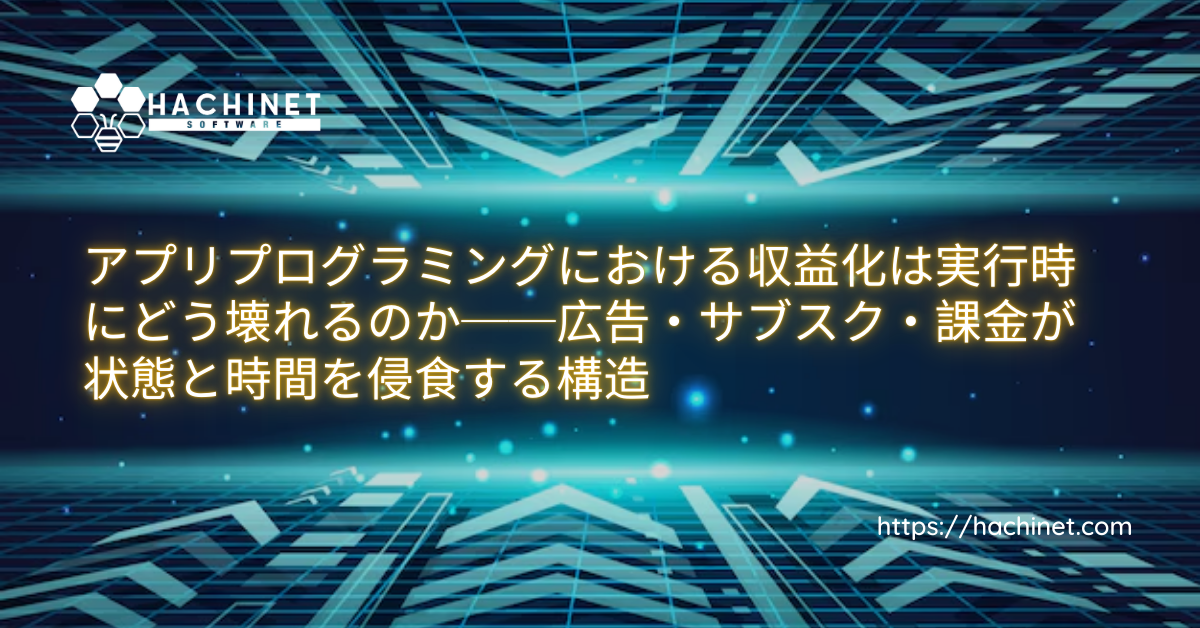
アプリプログラミングにおける収益化は実行時にどう壊れるのか──広告・サブスク・課金が状態と時間を侵食する構造
アプリプログラミングにおいて、収益化を組み込むという行為は「機能を増やす」ことではない。実行時の状態数を爆発的に増やし、時間軸を複数に分岐させる行為だ。この変化を設計で制御できなかった瞬間から、アプリは静かに壊れ始める。

MVPは試作品ではない──スタートアップのアプリプログラミングで最初に固定される3つの技術前提
スタートアップが最初に作るアプリを「MVPだから雑でいい」と考えると、ほぼ確実に作り直しになります。理由は単純で、アプリプログラミングではMVPであっても必ず固定されてしまう技術前提が存在するからです。本記事では、初期アプリで何を作るかではなく、何が不可逆に決まってしまうのかを、実装レベルで整理します。





