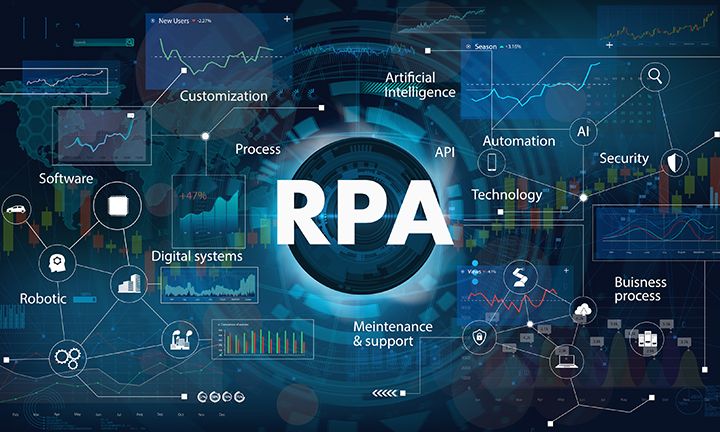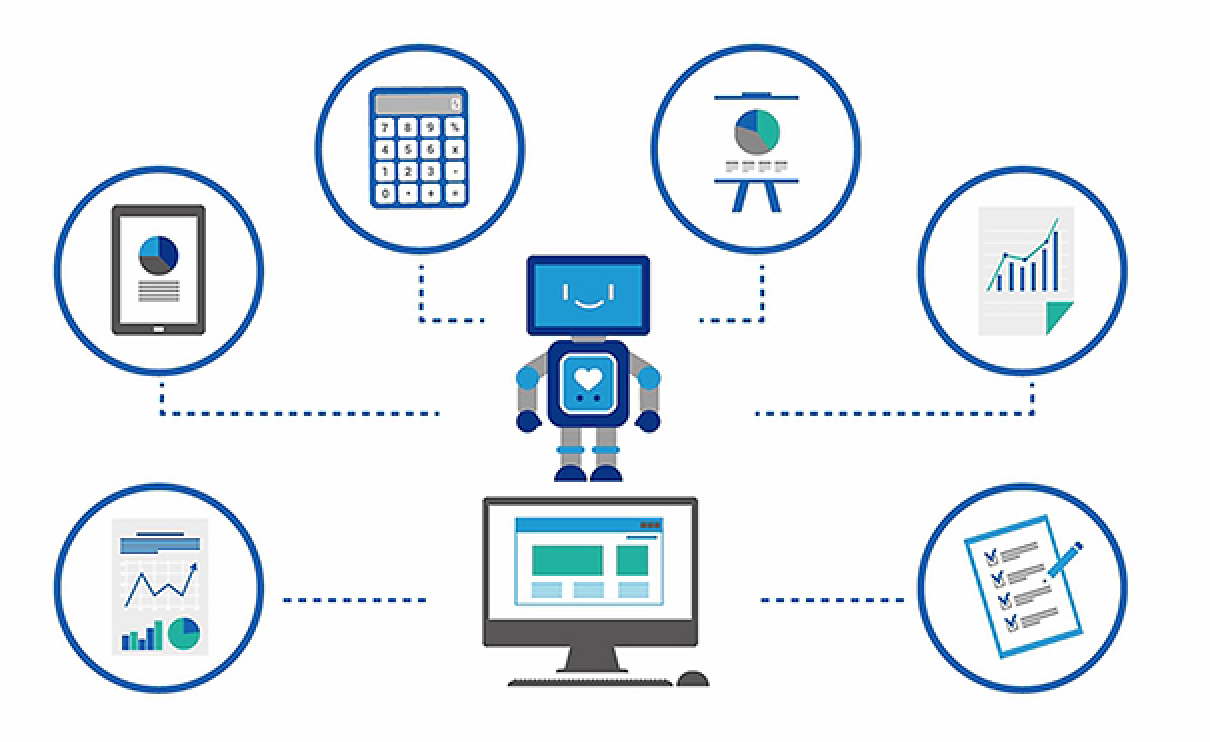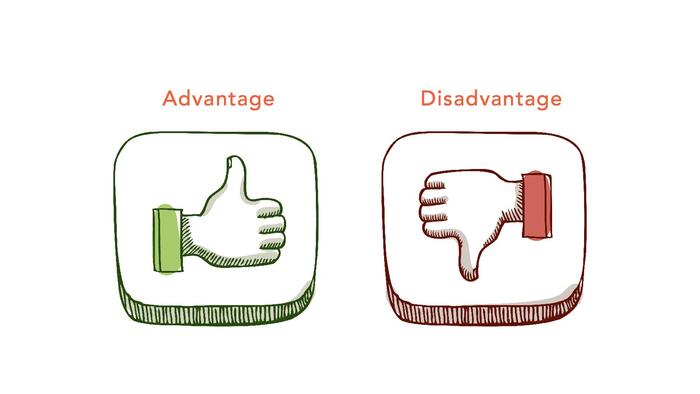RPAとは?流れ・メリットとデメリットを簡単にご紹介!
RPAは単純作業になりがちな定型業務をロボットによって自動化する取り組みを表す。RPAは、人間が行う業務処理を登録しておくだけで、業務自動化を実現することができます。現在は、商社、流通、金融、不動産、小売、製造まで多方面で業務自動化を拡大し、より広い範囲の業務に対応できる技術として活用され始めています。
2021年04月09日
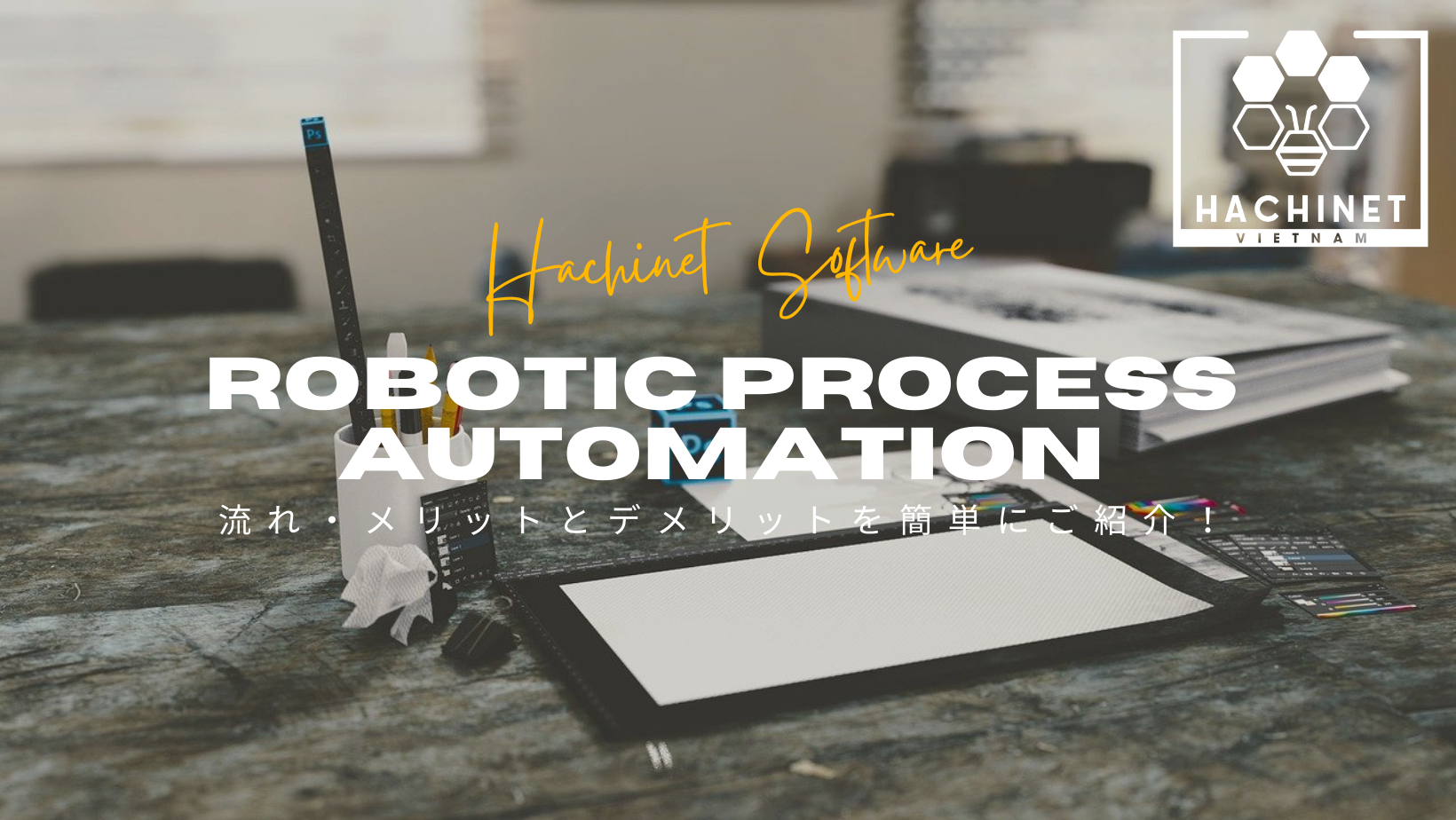
RPAは単純作業になりがちな定型業務をロボットによって自動化する取り組みを表す。RPAは、人間が行う業務処理を登録しておくだけで、業務自動化を実現することができます。現在は、商社、流通、金融、不動産、小売、製造まで多方面で業務自動化を拡大し、より広い範囲の業務に対応できる技術として活用され始めています。
RPAは単純作業になりがちな定型業務をロボットによって自動化する取り組みを表す。RPAは、人間が行う業務処理を登録しておくだけで、業務自動化を実現することができます。現在は、商社、流通、金融、不動産、小売、製造まで多方面で業務自動化を拡大し、より広い範囲の業務に対応できる技術として活用され始めています。
1. RPAとは?
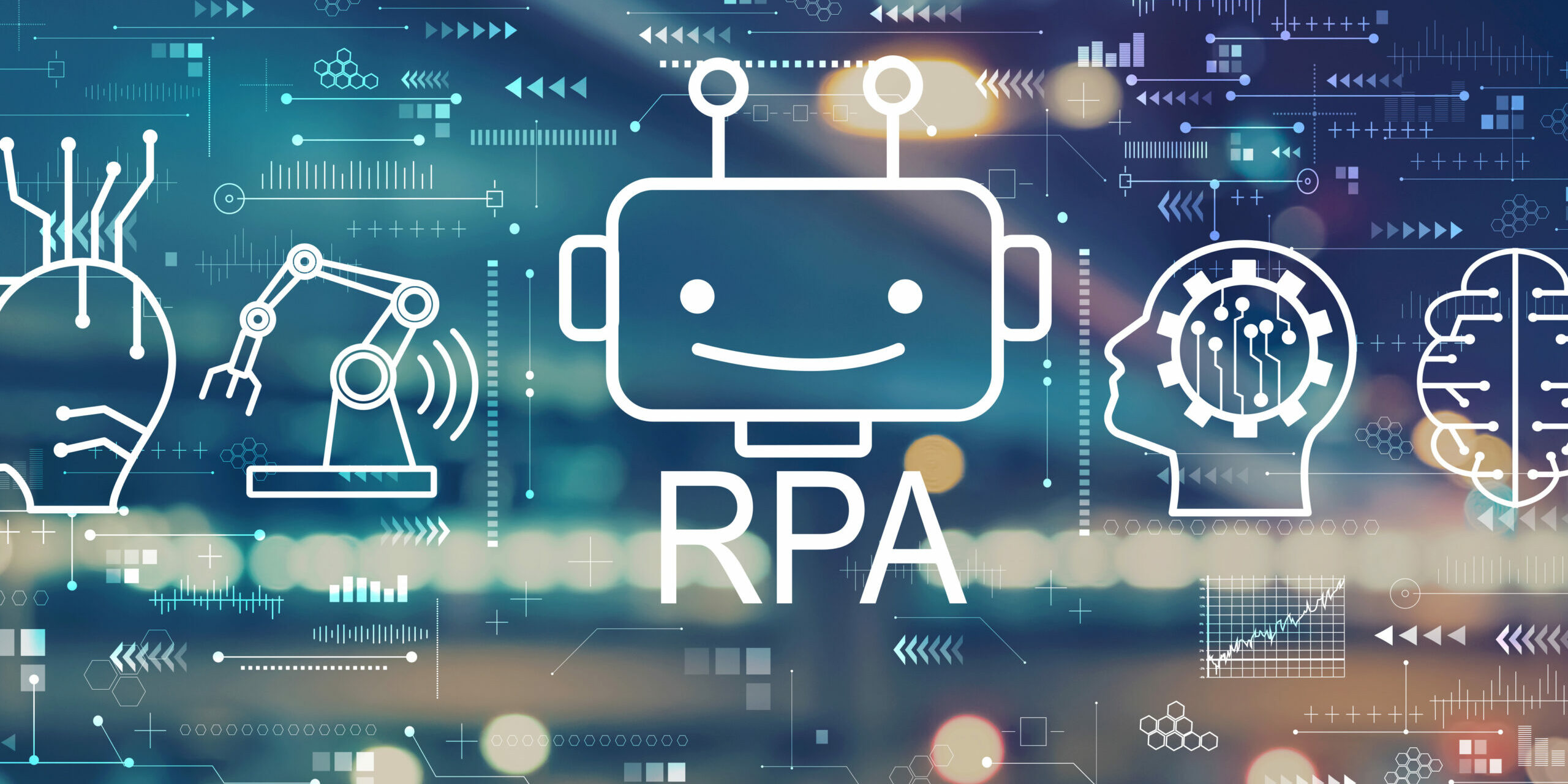
RPAとは「Robotic Process Automation /ロボティック・プロセス・オートメーション」の略語で、ホワイトカラーのデスクワーク(主に定型作業)を、ルールエンジンやAI(人工知能)などの技術を備えたソフトウェアのロボットが代行・自動化する概念、と定義されています。
このRPAという概念を実現するツールのことを、RPAツールと呼びます。現在、RPAという言葉が様々な形で利用されていますが、広義のRPAとはRPAという変革全体を表し、狭義のRPAというとRPAツールを表すケースが多いです。
2. RPAの3段階
2.1. Class 1:RPA(Robotic Process Automation)
class1と呼ばれるRPAは、定型業務をミスなく的確に遂行する、またいくつかのアプリケーション連携が必要とされる単純作業に対応します。人事・経理・総務・情報システムなどのバックオフィスの事務・管理業務や、販売管理や経費処理などに使われています。
2.2. Class 2:EPA(Enhanced Process Automation)
単純作業を覚えるだけでなく、膨大なデータをAIと連携し解析することが可能になります。
画像をカテゴリ毎に分類、AIと連携しユーザーの傾向を分析、など様々な機能があります。実際に、コールセンターやチャットボットといったシーンで利用されています。いずれも導入のために必要な辞書データやAI機械学習にかかる投資が必要なため、クラス1に比較すると導入難易度は上がるといわれています。
2.3. Class 3: CA(Cognitive Automation)
CAはRPAにAIのような自律的な判断力を備えたもので、プロセスの分析や改善、意思決定までを自動化するとともに、ディープラーニングや自然言語処理まで対応できるものもあります。膨大なデータの整理・分析だけでなく、得られたデータを生かした経営改善などにも活用できます。
3. RPA導入の流れ
3.1. 社内で専門のプロジェクトチームを立ち上げる
RPAの導入ではほとんどの部門・部署が対象となりますので、対象となる部門・部署のメンバーを集めて専門のプロジェクトチームを立ち上げる必要があるでしょう。担当となった方が情報の交通整理をしていきます。
3.2. 現状の業務プロセスを洗い出す
人間の手で行われている作業は担当者が頭で把握したとしても、フローとしてマニュアルがないことも多いはずです。まずは作業ごとにどのようなプロセスで業務を進めているのかを洗い出しましょう。この洗い出しのタイミングでは、単純作業で自動化できそうなもの、都度アレンジが必要で人間が作業したほうが効率的なものなどとざっくりで良いので把握しておくと良いでしょう。
3.3. RPAの導入範囲と開発会社・導入ツールを選定する
続いてはRPAの導入範囲(どの業務を自動化するのか)を決めます。自動化できる範囲すべてをRPAに任せたいところではありますが、導入にはコストがかかりますので、導入の費用と自分たちで行う場合の費用、それから工数などを加味しながら導入範囲を決定します。それから、RPAの開発をす依頼する開発会社、導入ツールを選定していきます。
3.4. テスト導入をする
そこまで決まったらRPAを導入することになりますが、最初からすべて導入してエラーが起こってしまったら大変なことになりますので、本格的に導入する前に一部の部署などと限定してテスト導入をします。
3.5. 課題点を洗い出してRPAを修正する
テスト導入し、実際に使ってみて気になる点や不具合を発見することがあります。テスト導入の段階ではそうした課題を洗い出しましょう。そして、本格導入の前に課題となった箇所を修正します
3.6. 修正後のRPAを踏まえて本格導入する範囲を決める
テスト導入で実際に使ってみた結果、それから修正後のRPAの仕様などを踏まえて、どの業務を自動化させるか、導入範囲を考え直します。このタイミングでRPAの専門プロジェクトチームに選ばれた方などを対象としてRPAの操作方法を研修し、各部門・各部署で本格導入への準備を整えます。運用に関してのルールやアクセス権限の決定、誰でも使えるようにするためのマニュアル作成も行います。
3.7. 本格導入して保守・運用・改善をしていく
最後は本格導入です。RPAを導入して、部門・部署がそれぞれの必要な設定をして実際に自動化を進めていきます。業務フローが変われば、それに合わせてRPAの動作ルールを変更するなど、保守・運用・改善をします。導入後にどれだけの効果が得られたかも検証しておきましょう。それによって必要となる工数や人員の管理をすることができますし、社内の他の部門・部署、それからグループ会社などで導入する際に役に立つでしょう。
4. メリット・デメリット
4.1. メリット
クオリティーの安定化
RPAは人為的なミスを防げるのがメリットの一つです。まったく同じ業務であっても24時間連続して進められます。人員を割かずに済む点も強みです。
作業の高速化
プログラミングされた内容であれば人間以上のスピードで作業を進めてくれます。RPAは決められたルールに従って動くため、予想しない挙動で問題になることは少ないです。
コストの削減
従業員の労働力を確保したまま効率化するため、人件費の削減に貢献します。業務のクオリティを下げずに速度のみが上がります。作業に必要だった人員が減るため、重要な業務に集中できます。
4.2. デメリット
業務が停止するリスクがある
RPAはITシステムであるため、システム障害やバグが発生すれば作業が止まる危険性があります。実際にサーバの能力を超えるような動作を実行した場合にサーバがダウンしてしまい、作業のデータを失う可能性もあります。RPAを導入するときは、キャパシティに余裕があるサーバを用意し、安全に運用できる環境を構築する必要があります。
情報漏えいの可能性がある
ネットワークに繋がったサーバにインストールしたRPAであれば、不正アクセスされる可能性はゼロではありません。不正アクセスされることで情報漏えいが起きるリスクがあるため、情報セキュリティの対策を万全にする必要があります。
5. まとめ
RPAの導入は業務効率化や生産性向上を実現するためのスタートであり、その未来を左右するのは導入後の運用にかかっています。一方で、取り扱いや管理、セキュリティ面での危険性があることも事実です。
オフショア開発をご検討されている方々はぜひ一度ご相談ください。
※以下通り弊社の連絡先
アカウントマネージャー: クアン(日本語・英語対応可)
電話番号: (+84)2462 900 388
お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。
- オフショア開発
- エンジニア人材派遣
- ラボ開発
- ソフトウェアテスト
電話番号: (+84)2462 900 388
メール: contact@hachinet.com
お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。
無料見積もりはこちらから
Tags
ご質問がある場合、またはハチネットに協力する場合
こちらに情報を残してください。折り返しご連絡いたします。
関連記事

Dartは本当に就職に強いのか?Flutter求人の構造・年収帯・生存戦略まで踏み込んで解説
Dart入門と検索する段階で、多くの人はすでに疑問を持っています。「学びやすいらしいが、それで就職できるのか」。結論を先に言えば、Dartは単体では市場価値を持ちません。評価対象はあくまで Flutter です。本記事では、日本・ベトナム・欧米市場の採用構造を具体的に分解し、年収レンジ感やスキル要件まで踏み込んで現実的に整理します。

Flutterで頭打ちになる人が見落としているDart基礎設計の決定的差
Flutterは学習初期の成功体験が早い技術です。しかし半年後、コードが肥大化し、再利用できず、状態管理が複雑になり、自分でも触りたくないプロジェクトになるケースは少なくありません。その分岐点はDart理解の深さです。Dart 入門レベルの文法理解で止まり、言語仕様や実行モデルに踏み込まなかった人ほど設計が破綻します。本記事では「なぜDart理解が不足するとFlutter開発が不安定になるのか」を技術構造レベルで解説します。

Dartのオブジェクト指向は「設計しない」ことで成立している
Dartのオブジェクト指向は、学習段階では拍子抜けするほど単純です。しかし実務で数万行規模になると、多くの言語で起きる「設計崩壊」が、Dartでは驚くほど起きにくい。本記事では、その理由を「美しい設計論」ではなく、どこで壊れ、どこで踏みとどまるのかという実装結果ベースで掘り下げます。
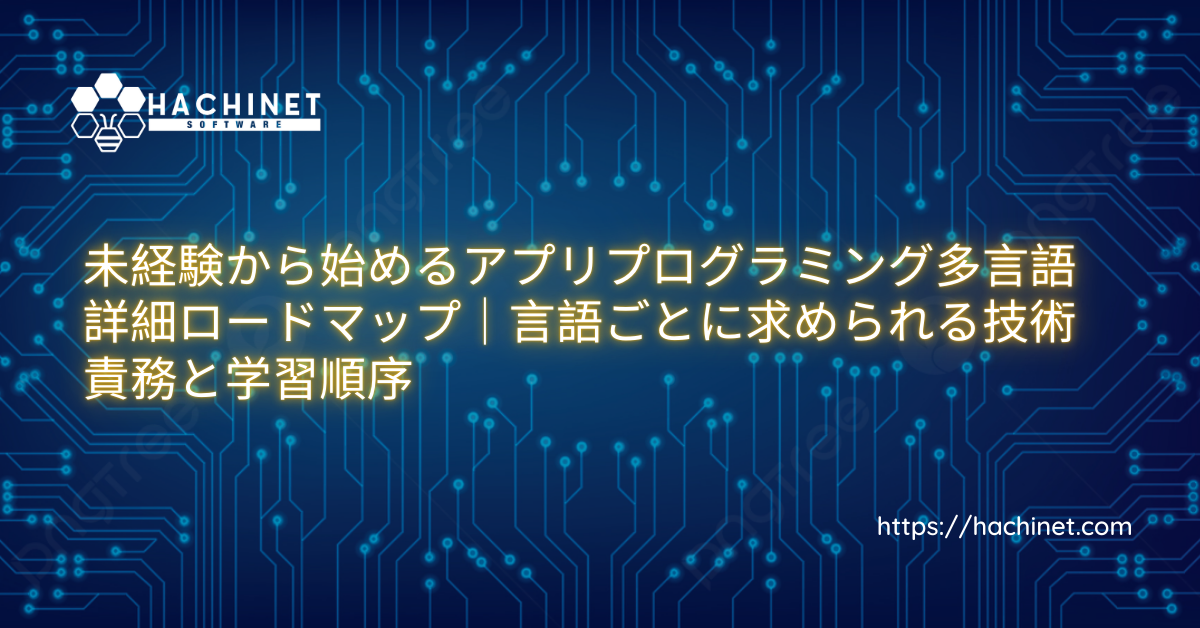
未経験から始めるアプリプログラミング多言語詳細ロードマップ|言語ごとに求められる技術責務と学習順序
未経験からアプリプログラミングを学ぶ際、多くの人は「どの言語を覚えればアプリが作れるか」という問いを立てます。しかし実務では、アプリは単一言語で完結することはなく、複数の言語が異なる責務を分担する構造体として存在します。本記事では、言語を単なるスキルではなく、アプリを成立させるための必須構成要素として整理します。
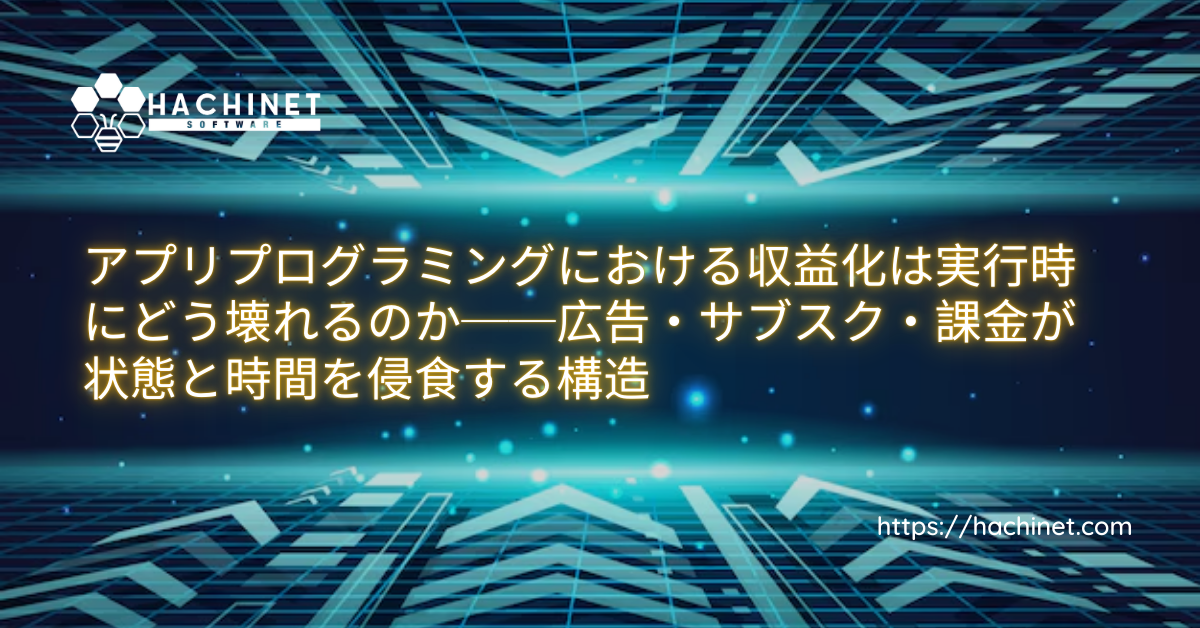
アプリプログラミングにおける収益化は実行時にどう壊れるのか──広告・サブスク・課金が状態と時間を侵食する構造
アプリプログラミングにおいて、収益化を組み込むという行為は「機能を増やす」ことではない。実行時の状態数を爆発的に増やし、時間軸を複数に分岐させる行為だ。この変化を設計で制御できなかった瞬間から、アプリは静かに壊れ始める。

MVPは試作品ではない──スタートアップのアプリプログラミングで最初に固定される3つの技術前提
スタートアップが最初に作るアプリを「MVPだから雑でいい」と考えると、ほぼ確実に作り直しになります。理由は単純で、アプリプログラミングではMVPであっても必ず固定されてしまう技術前提が存在するからです。本記事では、初期アプリで何を作るかではなく、何が不可逆に決まってしまうのかを、実装レベルで整理します。