ECシステムとは?メリット・デメリット・拡大した理由をご理解
一人一人は「対面での商売」を数千年にわたって続けてきました。それが今ではどうでしょう?インターネットの発展とスマートフォンの急速な普及により、せっかく店に足を運ぶ必要はなく、売買が完結する時代です。今回は、ECシステムとは何なのか?メリット•デメリット•拡大した理由今後はじめて取り組む方に向けてその概要について説明し、ECシステムに欠かせない基礎知識もご紹介します。
2021年04月09日

一人一人は「対面での商売」を数千年にわたって続けてきました。それが今ではどうでしょう?インターネットの発展とスマートフォンの急速な普及により、せっかく店に足を運ぶ必要はなく、売買が完結する時代です。今回は、ECシステムとは何なのか?メリット•デメリット•拡大した理由今後はじめて取り組む方に向けてその概要について説明し、ECシステムに欠かせない基礎知識もご紹介します。
一人一人は「対面での商売」を数千年にわたって続けてきました。それが今ではどうでしょう?インターネットの発展とスマートフォンの急速な普及により、せっかく店に足を運ぶ必要はなく、売買が完結する時代です。今回は、ECシステムとは何なのか?メリット•デメリット•拡大した理由はじめて取り組む方に向けてその概要について説明し、ECシステムに欠かせない基礎知識もご紹介します。
1. ECシステムとは何か?

ECシステムとは「Electronic Commerce」の略です。Electronicは電子的、Commerceは商取引を指すことから、「電子商取引」という意味があります。Eコマースとはネットを通じて行われるモノやサービスの売買の総称です。端的に言うと、ECサイトとはネットを使ったモノやサービスの販売サイトのことです。
通信販売は、カタログをWebサイト上の商品紹介ページに置き換え、ハガキや電話をメールや申し込みフォームに置き換えれば、インターネット通販になります。つまり、紙のカタログを使った通信販売のある機能をインターネット(電子的なもの)に置き換えたものがECだと考えられます。
2. ECシステムのメリットとデメリット
2.1. ECシステムの四つのメリット
・ お客さんが店に行くことが必要ない
ECシステムはインターネット上のお店です。ユーザーがお店に行かなくても、好きな商品を探して買うすることが可能です。例えば、実店舗の場合で「欲しい服を探す」とか、「流行している靴」には複数をお店に足を運んで予算や自分の体形に合う服や靴を探さなくてはなりません。しかし、インターネットの場合、スマートフォン1つで移動することなく、複数のECサイトの中から簡単にに欲しい服や靴といった自分が好きな商品を選ぶことができます。
・ ニッチな商品を探して買うことができる
CDやレコード等の珍しいオーディオ商品や、一部のマニア向けの商品や部品は通常、専門店に行かないとなかなか手に入れることはできませんでした。しかし、インターネットではそういったニッチ商品であっても、世界中のECシステムから探すことができます。同じECシステムを使う人のコメントを読んだ後で、選ぶかどうか決められます。
・ 世界中の商品を簡単に手には入れられる
ECシステムは使いやすくて、手順も簡単なので、東京の原宿にしか売っていない服でも、ECシステムであれば、地方に住んでいても買うことが可能です。
・安値で商品を買いやすい
ユーザーは最安値の店を探して、商品を手に入れることができます。ECシステムでは商品は安くなりやすく、お店が送料負担をする場合もあります。特別な日にもセールされ物が多いので、お客の購買欲も急速に増えてきます。
2.2. ECシステムの三つのデメリット
上記メリットに加えてますが、その以外はECシステムのデメリットもがあります。次にECシステムのデメリットをご紹介します。
・配達の時間がかかる
ECシステムは配達の時間があるため、すぐには手に入りません。物やサービスによりますが、通常のECサイトでの買い物は家に届くまでに3日ぐらい待たなければなりません。
・ 競争相手が多い
実店舗の場合、エリアを選べば、ライバルが存在しない所も多くあるでしょうが、ECシステムはそのように簡単ではないです。例えば、「大きなテーブル」をGoogleのホームページで探して、広告や検索結果がたくさん出てきます。ということは、これらの会社全てがライバルです。
・届いた実物とイメージが異なること
ファッション商品は実店舗だと試着して自分の体形やセンスにあうものを選ぶことができるため、自分が納得したものを買うことができます。しかし、ECシステムの場合は、写真や商品説明だけなので、イメージを掴みにくいことがあり「サイズがちょっと大きいなあ」、「思ったより色が濃いな」と商品を買った後で、満足しないという気持ちもあるでしょう。
3. ECシステムの種類

ECは、前述したようにEDIのような商取引も含まれますが、ここでは「EC=ショッピングサイトによる通信販売」と考えて話を進めます。そして、ショッピングサイトといっても、実はいろいろな種類があります。
→ パッケージタイプ:ある程度サイトが作りこまれた状態であり、独自のカスタマイズも加えられることから、柔軟性とコストのバランスが取れたタイプです。
→ オープンソースタイプ:オープンソースとは「ライセンス費用がかからず、無償で商用利用できるソフトウェア」という意味があるであり、これを活用してショッピングサイトを作ります。
→ クラウドタイプ:最近、パッケージタイプに搭載されている機能をインターネット上で提供し、ソフトウェアを購入せずにショッピングサイトというサービスが増えています。それはクラウドタイプです。
→ モールタイプ:楽天市場などのモール型ショッピングサイトが備えている機能で作られるサイトのことです。
4. ECシステムが世界中に拡大した理由

ECシステムが世界中に拡大した理由を「以前に比べてショッピングサイトの立ち上げ難易度が大幅に下がったから」や、「ECならば日本全国に商圏を広げられるから」などと理解する人が多いでしょう。しかし、本当の理由はそうした事業者側の都合ではなく、単純に「消費者がそれを求めているから」だと考えられます。
1990年代後半から2000年初頭にかけ、インターネットが急激に流行したことなので、その状況が大きく変わります。消費者は欲しい情報を欲しい時に入手できるようになり、消費者自身がインフォメーションを簡単に発信できるようになります。それで、消費者の様々な行動は、自然とネット上へと移行していきます。
ECシステムの市場は今後も拡大を続けますし、新しい技術の登場によってトレンドが次々に変化していきます。そのおかげで、商機もどんどん増えていきますので、今とこれからのECシステムについてよく検討した上で、最適なEC戦略を決めた方がいいとおもいます。
5. ECシステムサービス導入の流れ

・コンセプトを考える:まず、「何のためにサイトを制作するのか」「どのようなサイトを作りたいか」などを検討した上で、コンセプトからECサイトのデザインや機能を決定していきましょう。
・要件定義:機能によっては、次の工程で決めるプラットフォームの選定に影響するため、最低限必要な機能とできるだけ盛り込みたい機能などを費用面も考慮しながら検討します。
・プラットフォームを決定する:ECプラットフォームによっては、機能やデザインが制限されてしまうため、ここでしっかり決めないと、あとから大幅な修正が必要になる場合もあります。
・商品の登録:事前に商品の画像や説明文のデータを作成しておき、CSVなど一括登録しやすい形にしておくと良いでしょう。
・オペレーションテストを行う:実店舗と同じようにスタッフの教育も必要です。トラブルが発生した場合の対応まで、事前に確認しておきます。
・オープン:ようやくECサイトをリリースし、運用段階へ移行します。リリース前には顧客に告知したり、SNSなどで拡散したりして、オープンをたくさんの人に宣伝しましょう。
6. まとめ
私たちの生活の中で、今や「なくてはならない」存在になりつつあるECシステムです。しかし、馴染み深いとはいえ、運営となると、そう簡単にはいきません。わりと参入障壁が低いとされることから、個人も含めていろいろな企業がECシステムを導入しており、競争は激化しています。そんな中、売り上げを上げて勝ち残っていくことは決して楽な仕事とは言えません。今日の理解された内容を着実に実行し、お客様の声に耳を傾けながら日々改良を続ける努力を怠らなければ、結果は自ずと表れるはずです。
オフショア開発をご検討されている方々はぜひ一度ご相談ください。
※以下通り弊社の連絡先
アカウントマネージャー: クアン(日本語・英語対応可)
電話番号: (+84)2462 900 388
お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。
- オフショア開発
- エンジニア人材派遣
- ラボ開発
- ソフトウェアテスト
電話番号: (+84)2462 900 388
メール: contact@hachinet.com
お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。
無料見積もりはこちらから
Tags
ご質問がある場合、またはハチネットに協力する場合
こちらに情報を残してください。折り返しご連絡いたします。
関連記事

Dartは本当に就職に強いのか?Flutter求人の構造・年収帯・生存戦略まで踏み込んで解説
Dart入門と検索する段階で、多くの人はすでに疑問を持っています。「学びやすいらしいが、それで就職できるのか」。結論を先に言えば、Dartは単体では市場価値を持ちません。評価対象はあくまで Flutter です。本記事では、日本・ベトナム・欧米市場の採用構造を具体的に分解し、年収レンジ感やスキル要件まで踏み込んで現実的に整理します。

Flutterで頭打ちになる人が見落としているDart基礎設計の決定的差
Flutterは学習初期の成功体験が早い技術です。しかし半年後、コードが肥大化し、再利用できず、状態管理が複雑になり、自分でも触りたくないプロジェクトになるケースは少なくありません。その分岐点はDart理解の深さです。Dart 入門レベルの文法理解で止まり、言語仕様や実行モデルに踏み込まなかった人ほど設計が破綻します。本記事では「なぜDart理解が不足するとFlutter開発が不安定になるのか」を技術構造レベルで解説します。

Dartのオブジェクト指向は「設計しない」ことで成立している
Dartのオブジェクト指向は、学習段階では拍子抜けするほど単純です。しかし実務で数万行規模になると、多くの言語で起きる「設計崩壊」が、Dartでは驚くほど起きにくい。本記事では、その理由を「美しい設計論」ではなく、どこで壊れ、どこで踏みとどまるのかという実装結果ベースで掘り下げます。
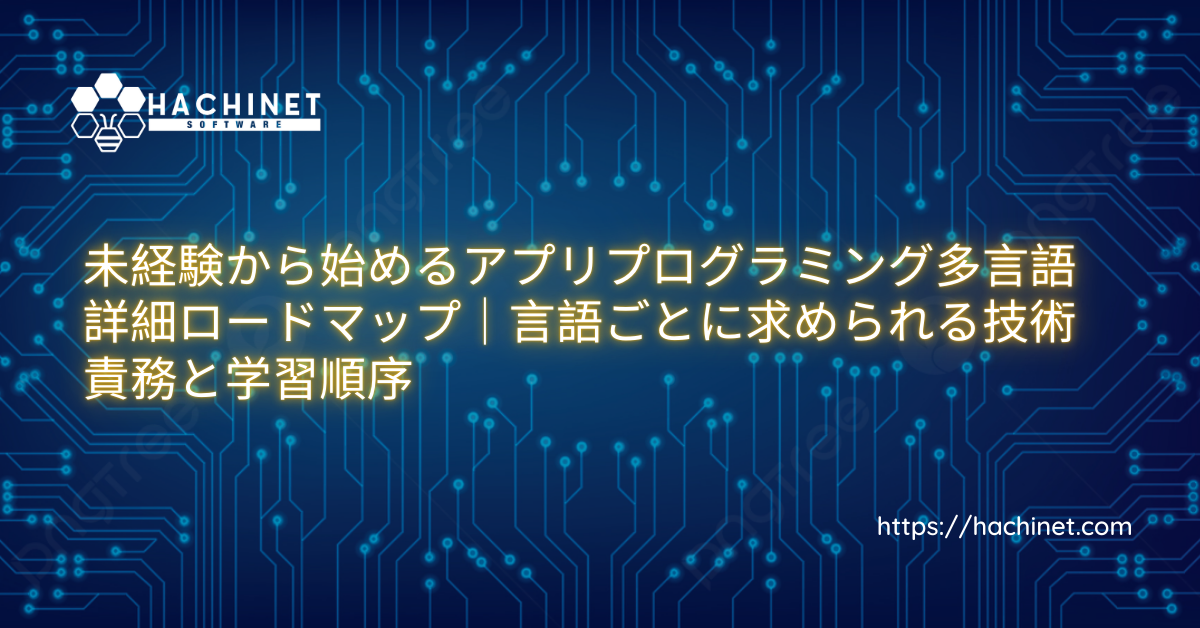
未経験から始めるアプリプログラミング多言語詳細ロードマップ|言語ごとに求められる技術責務と学習順序
未経験からアプリプログラミングを学ぶ際、多くの人は「どの言語を覚えればアプリが作れるか」という問いを立てます。しかし実務では、アプリは単一言語で完結することはなく、複数の言語が異なる責務を分担する構造体として存在します。本記事では、言語を単なるスキルではなく、アプリを成立させるための必須構成要素として整理します。
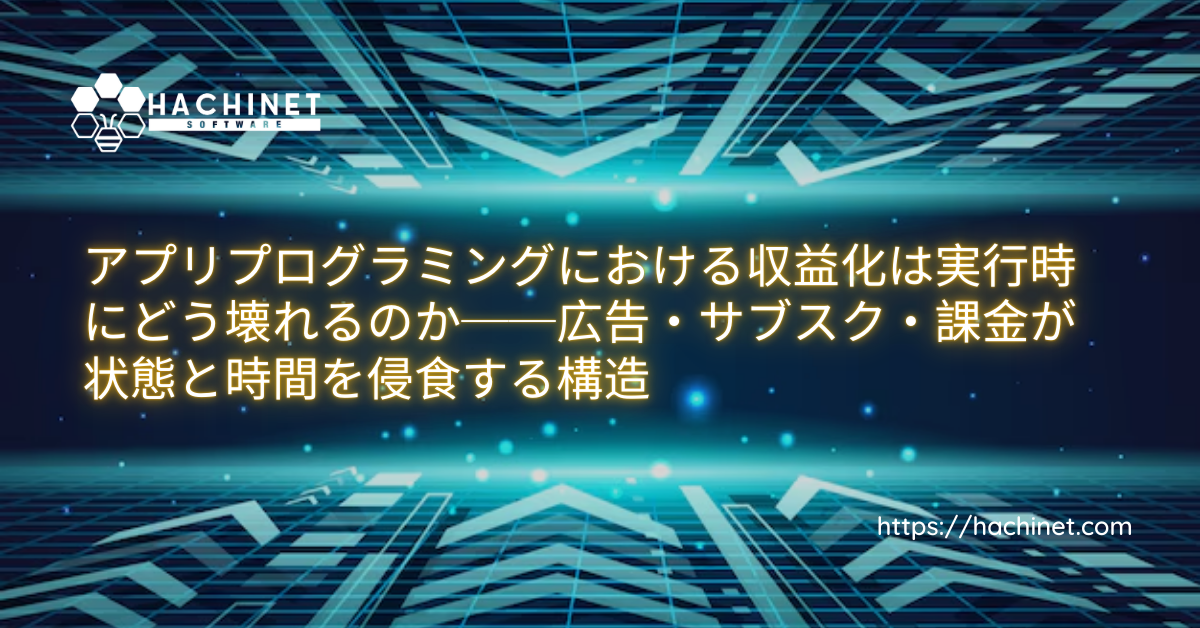
アプリプログラミングにおける収益化は実行時にどう壊れるのか──広告・サブスク・課金が状態と時間を侵食する構造
アプリプログラミングにおいて、収益化を組み込むという行為は「機能を増やす」ことではない。実行時の状態数を爆発的に増やし、時間軸を複数に分岐させる行為だ。この変化を設計で制御できなかった瞬間から、アプリは静かに壊れ始める。

MVPは試作品ではない──スタートアップのアプリプログラミングで最初に固定される3つの技術前提
スタートアップが最初に作るアプリを「MVPだから雑でいい」と考えると、ほぼ確実に作り直しになります。理由は単純で、アプリプログラミングではMVPであっても必ず固定されてしまう技術前提が存在するからです。本記事では、初期アプリで何を作るかではなく、何が不可逆に決まってしまうのかを、実装レベルで整理します。




