企業がEORサービスを利用すべきタイミング
近年、グローバル化が進展する中で、多くの企業が海外市場への進出を目指しています。特に、ベトナムなどの新興市場では、質の高い人材を安価に確保できることから、多くの企業が注目しています。しかし、異国での事業展開には様々な課題が伴います。特に、現地の法令遵守や人事管理の複雑さは、企業にとって大きな負担となります。このような状況下で、雇用代行 (EOR) サービスは、企業にとって非常に有効な解決策となります。本記事では、企業がEORサービスを利用すべき具体的なタイミングとその利点について探っていきます。
2024年10月11日

近年、グローバル化が進展する中で、多くの企業が海外市場への進出を目指しています。特に、ベトナムなどの新興市場では、質の高い人材を安価に確保できることから、多くの企業が注目しています。しかし、異国での事業展開には様々な課題が伴います。特に、現地の法令遵守や人事管理の複雑さは、企業にとって大きな負担となります。このような状況下で、雇用代行 (EOR) サービスは、企業にとって非常に有効な解決策となります。本記事では、企業がEORサービスを利用すべき具体的なタイミングとその利点について探っていきます。
1. EORとは?
Employer of Record (EOR): EORとは、日本語で「雇用代行」と呼んで、別の企業のために従業員を雇用する組織または会社であり、採用、給与支払い、税務管理、福利厚生、および労働法の遵守に関連するすべての法的および行政的な問題について責任を負います。従業員は「クライアント」企業で働き続けますが、EOR会社が法的手続きに関連するすべての業務を処理します。
本記事では、企業がどのような状況でEORサービスを利用すべきかを具体的に分析し、特にベトナムのIT人材やITエンジニアに焦点を当てて考察します。
2. 企業がEORサービスを利用すべきタイミング

企業が国際市場に進出する際
企業がベトナムなどの海外市場に進出し、現地のITエンジニアを雇用したい場合、EORは非常に有効です。現地法人を設立せずに、迅速に人材を採用することができます。特に、ベトナムは質の高いIT人材を多く輩出しており、企業が競争力を維持するための優れた選択肢となります。
企業が迅速に人材を採用したい場合
新しいプロジェクトの開始や、急な人手不足に対応するために、企業は素早くITエンジニアを採用する必要があります。EORを利用することで、スムーズな採用プロセスが実現し、企業は競争力を保つことができます。
企業が現地の法律に関する経験がない場合
ベトナムの労働法は複雑であり、外国企業にとっては理解が難しい場合があります。EORを利用することで、企業は現地の法律や規制を熟知した専門家に管理を任せることができ、安心してビジネスを展開できます。
企業が法的リスクを軽減したい場合
EORサービスは、労働法や税法の遵守を確保するための強力な手段です。企業は、法的なトラブルを避けることができ、安心してIT人材を管理することができます。
企業が人件費を最適化したい場合
EORを利用することで、現地法人を設立する際のコストを削減できます。特に、ベトナムのITエンジニアは、高いスキルを持ちながらもコストが抑えられているため、企業にとって非常に魅力的な選択肢となります。
企業が人材管理に柔軟性を求める場合
EORは、企業が必要に応じて人員を増減できる柔軟な管理体制を提供します。特にIT業界では、短期間のプロジェクトに対応するために、フレキシブルな人材管理が求められます。
III. EORサービスの利用メリットとデメリット
1.メリット
行政手続きの簡素化
EORを利用することで、企業は複雑な行政手続きを気にせずに人材を採用できます。これにより、ビジネスの運営に専念することが可能です。
管理の効率化
EORによって、企業は従業員の給与計算や福利厚生の管理を外部に委託することができ、本業に集中できます。特に、IT人材の管理は専門的な知識を要するため、EORがその役割を担うことで効率化が図れます。
給与と福利厚生の管理支援
EORは、従業員が適切に給与を受け取り、福利厚生を受けられるように管理します。これにより、企業は従業員の満足度を高めることができます。
2.デメリット
EORサービスは企業に多くの利点をもたらしますが、このサービスにはいくつかの不利な点も残っています。
企業文化の一貫性の欠如
EORを通じて雇用された従業員は、企業の直接の従業員ではないため、企業文化や価値観の共有が難しくなる場合があります。これは、チームの一体感や結束力に影響を及ぼす可能性があります。
雇用契約の柔軟性が低下
EORサービスを利用することで、従業員の雇用契約や条件が一律になることがあります。これにより、特定の従業員のニーズに応じたカスタマイズが難しくなる場合があります。
どのようなサービスにも利点と欠点がありますが、私は企業がEORサービスの利用を検討すべきだと思います。このサービスが提供する利点、特に海外市場に進出したい企業や、ベトナムのIT人材と連携したい企業にとっては非常に重要です。
EORサービスの活用は、企業の競争力を高め、国際的なビジネス展開を支える重要な要素となるでしょう。特に、優秀なITエンジニアを活用することで、企業は新たな成長を遂げることが期待されます。
- オフショア開発
- エンジニア人材派遣
- ラボ開発
- ソフトウェアテスト
電話番号: (+84)2462 900 388
メール: contact@hachinet.com
お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。
無料見積もりはこちらから
Tags
ご質問がある場合、またはハチネットに協力する場合
こちらに情報を残してください。折り返しご連絡いたします。
関連記事

Dartは本当に就職に強いのか?Flutter求人の構造・年収帯・生存戦略まで踏み込んで解説
Dart入門と検索する段階で、多くの人はすでに疑問を持っています。「学びやすいらしいが、それで就職できるのか」。結論を先に言えば、Dartは単体では市場価値を持ちません。評価対象はあくまで Flutter です。本記事では、日本・ベトナム・欧米市場の採用構造を具体的に分解し、年収レンジ感やスキル要件まで踏み込んで現実的に整理します。

Flutterで頭打ちになる人が見落としているDart基礎設計の決定的差
Flutterは学習初期の成功体験が早い技術です。しかし半年後、コードが肥大化し、再利用できず、状態管理が複雑になり、自分でも触りたくないプロジェクトになるケースは少なくありません。その分岐点はDart理解の深さです。Dart 入門レベルの文法理解で止まり、言語仕様や実行モデルに踏み込まなかった人ほど設計が破綻します。本記事では「なぜDart理解が不足するとFlutter開発が不安定になるのか」を技術構造レベルで解説します。

Dartのオブジェクト指向は「設計しない」ことで成立している
Dartのオブジェクト指向は、学習段階では拍子抜けするほど単純です。しかし実務で数万行規模になると、多くの言語で起きる「設計崩壊」が、Dartでは驚くほど起きにくい。本記事では、その理由を「美しい設計論」ではなく、どこで壊れ、どこで踏みとどまるのかという実装結果ベースで掘り下げます。
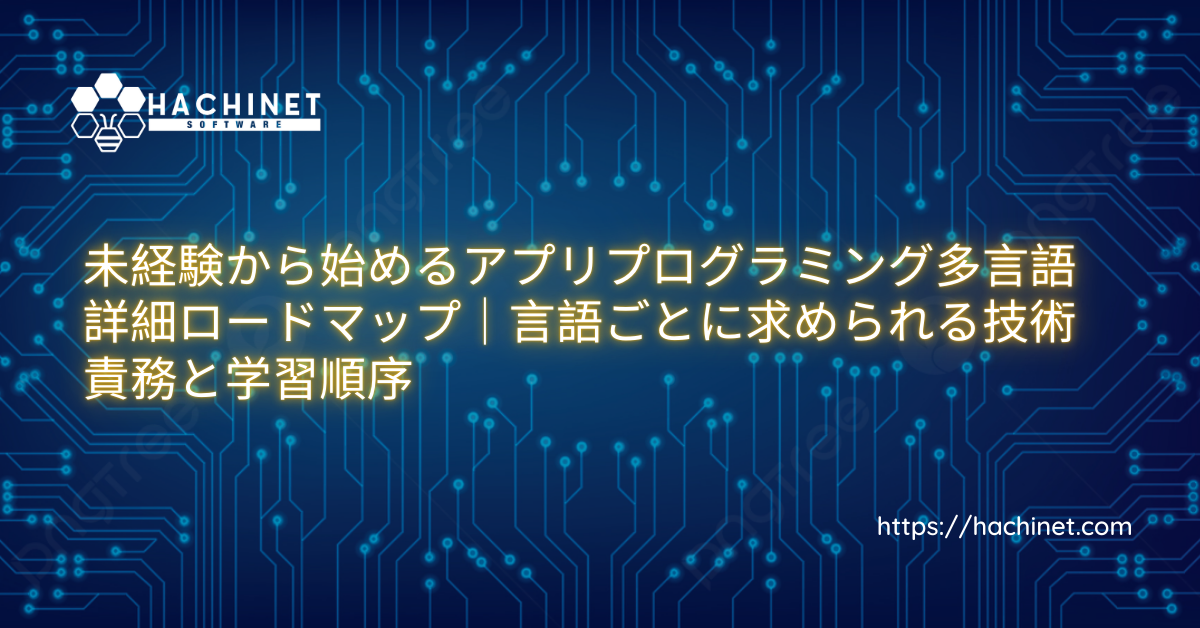
未経験から始めるアプリプログラミング多言語詳細ロードマップ|言語ごとに求められる技術責務と学習順序
未経験からアプリプログラミングを学ぶ際、多くの人は「どの言語を覚えればアプリが作れるか」という問いを立てます。しかし実務では、アプリは単一言語で完結することはなく、複数の言語が異なる責務を分担する構造体として存在します。本記事では、言語を単なるスキルではなく、アプリを成立させるための必須構成要素として整理します。
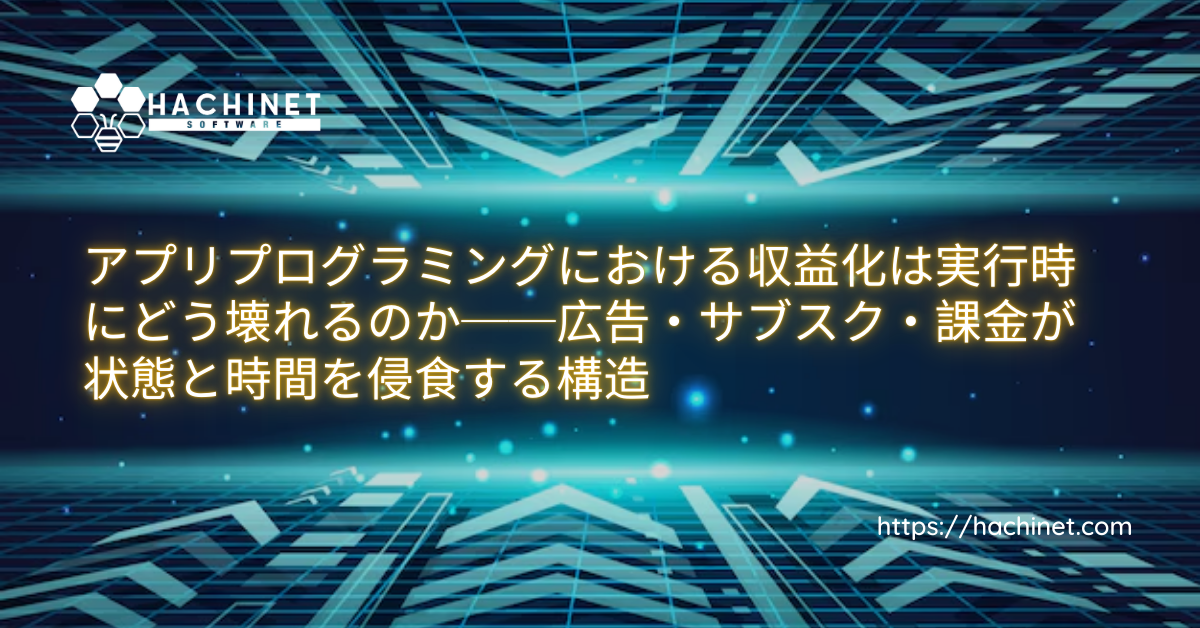
アプリプログラミングにおける収益化は実行時にどう壊れるのか──広告・サブスク・課金が状態と時間を侵食する構造
アプリプログラミングにおいて、収益化を組み込むという行為は「機能を増やす」ことではない。実行時の状態数を爆発的に増やし、時間軸を複数に分岐させる行為だ。この変化を設計で制御できなかった瞬間から、アプリは静かに壊れ始める。

MVPは試作品ではない──スタートアップのアプリプログラミングで最初に固定される3つの技術前提
スタートアップが最初に作るアプリを「MVPだから雑でいい」と考えると、ほぼ確実に作り直しになります。理由は単純で、アプリプログラミングではMVPであっても必ず固定されてしまう技術前提が存在するからです。本記事では、初期アプリで何を作るかではなく、何が不可逆に決まってしまうのかを、実装レベルで整理します。



