ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(外出禁止等)
【ポイント】 ●報道によれば,ベトナム政府は,今後, ①市民の外出を最大限制限する, ②外出せざるを得ない場合,マスクを常に着用し,他人と接触する際にはできるだけ2メートルの間隔をあける, ③20名以上の会議・イベント等の開催を中止し,特に,事務所ビル,学校,病院等の周辺で10人以上が集まることを禁止する, ④ハノイ市,ホーチミン市等において,食料,薬品,医療サービスを除き,全ての各種サービスの商店等を閉店する,等の措置を求めるとのことです(以下2に詳細)。 ●ベトナム在住の方にあっては,ご注意ください。 ●本件に関し,現時点で当館が入手している情報は,記載のとおりです。
2020年03月26日

【ポイント】 ●報道によれば,ベトナム政府は,今後, ①市民の外出を最大限制限する, ②外出せざるを得ない場合,マスクを常に着用し,他人と接触する際にはできるだけ2メートルの間隔をあける, ③20名以上の会議・イベント等の開催を中止し,特に,事務所ビル,学校,病院等の周辺で10人以上が集まることを禁止する, ④ハノイ市,ホーチミン市等において,食料,薬品,医療サービスを除き,全ての各種サービスの商店等を閉店する,等の措置を求めるとのことです(以下2に詳細)。 ●ベトナム在住の方にあっては,ご注意ください。 ●本件に関し,現時点で当館が入手している情報は,記載のとおりです。
【ポイント】
●報道によれば,ベトナム政府は,今後,
①市民の外出を最大限制限する,
②外出せざるを得ない場合,マスクを常に着用し,他人と接触する際にはできるだけ2メートルの間隔をあける,
③20名以上の会議・イベント等の開催を中止し,特に,事務所ビル,学校,病院等の周辺で10人以上が集まることを禁止する,
④ハノイ市,ホーチミン市等において,食料,薬品,医療サービスを除き,全ての各種サービスの商店等を閉店する,等の措置を求めるとのことです(以下2に詳細)。
●ベトナム在住の方にあっては,ご注意ください。
●本件に関し,現時点で当館が入手している情報は,記載のとおりです。
【本文】
1 ベトナムにおける感染状況
ベトナム保健省の発表によれば,3月26日午後7時現在におけるベトナム国内での新型コロナウイルスの陽性事例は計153名(うち17名は治癒)です。
2 ベトナム政府の措置(報道による)
(1)3月25日に開催されたCOVID-19対策国家指導委員会会合において,ダム副首相は,国民に対して,特に以下について留意するよう求めたとのことです。
ア 外出を最大限制限し,真に必要なときのみ外出する。
イ 外出せざるを得ない場合,マスクを常に着用し,他人と接触する際にはできるだけ2メートルの間隔をあける。
(2)3月26日に開催されたCOVID-19政府常務委員会において,フック首相は以下を述べたとのことです。これらの措置は,3月28日0時(深夜)から数週間実施し,延長も検討するとのことです。
ア 20名以上が集まる会議・イベント等の開催を中止する。
イ ハノイ市,ホーチミン市,ハイフォン市,カントー市,ダナン市において,食料,薬品,医療サービスを除き,全ての各種サービスの商店等を閉店する。
ウ 交通運輸省は,2大都市(ハノイ,ホーチミン)を出発する,各地行きの航空便を制限する。
エ 事務所ビル,学校,病院等の周辺で10人以上集まることを禁止する。
オ 人々は移動を少なくし,オンラインや他の適切な勤務様式に変えていく必要がある。

(連絡先)
在ベトナム日本国大使館
新型コロナ対応メールアドレス:covid19@ha.mofa.go.jp
電話番号(代表):+84-24-3846-3000
(※)受付時間:平日(土日及び祝日の休館日を除く。)8時30分~17時15分
(連絡先)
在ベトナム日本国大使館
新型コロナ対応メールアドレス:covid19@ha.mofa.go.jp
電話番号(代表):+84-24-3846-3000
(※)受付時間:平日(土日及び祝日の休館日を除く。)8時30分~17時15分
- オフショア開発
- エンジニア人材派遣
- ラボ開発
- ソフトウェアテスト
電話番号: (+84)2462 900 388
メール: contact@hachinet.com
お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。
無料見積もりはこちらから
Tags
ご質問がある場合、またはハチネットに協力する場合
こちらに情報を残してください。折り返しご連絡いたします。
関連記事
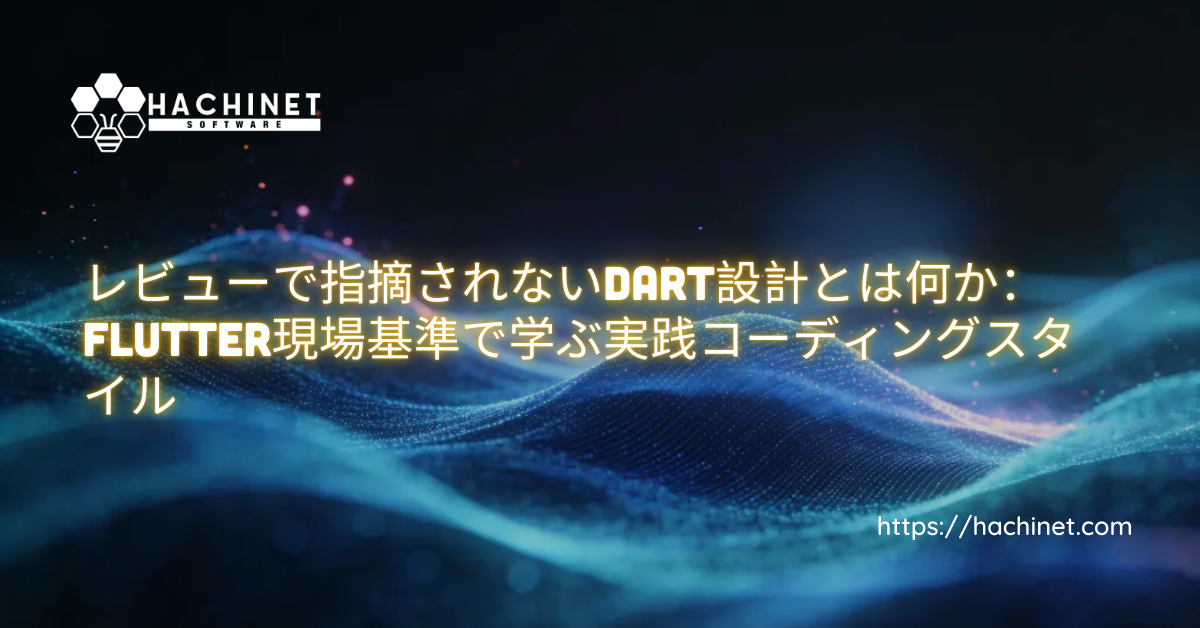
レビューで指摘されないDart設計とは何か:Flutter現場基準で学ぶ実践コーディングスタイル
Dart 入門で文法を学び、Flutterで画面を作れるようになると、多くの開発者が「それなりに動くアプリ」を作れるようになります。しかし実務では、それでは不十分です。レビューで問われるのは、可読性、変更耐性、責務分離、そしてチーム全体で維持できる一貫性です。本記事では、Flutterプロジェクトで実際に評価されるDartコーディングスタイルを、抽象論ではなく具体基準として掘り下げます。
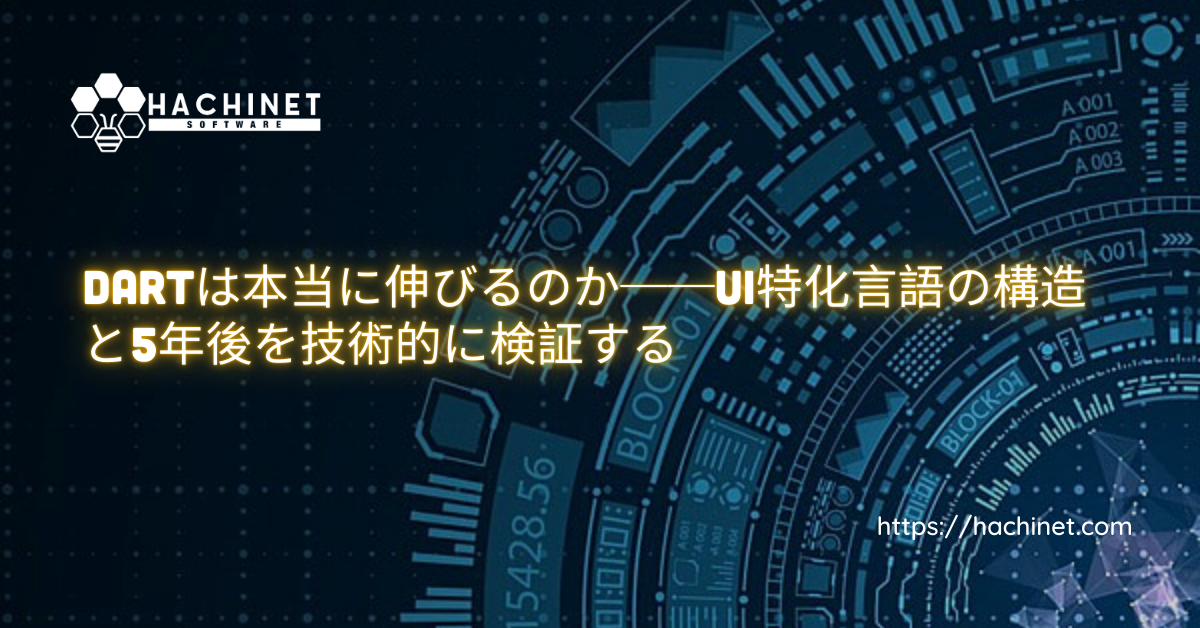
Dartは本当に伸びるのか──UI特化言語の構造と5年後を技術的に検証する
Dartは巨大言語ではありません。それでも一定の存在感を維持しているのは、設計思想が一貫しているからです。Dart 入門を検索する人の多くはFlutter開発を前提にしているはずです。本記事では、感覚的な「将来性がありそう」という議論ではなく、言語設計・市場構造・採用実態を踏まえ、Dartが今後5年でどの位置に収まるのかを技術視点で具体的に検証します。
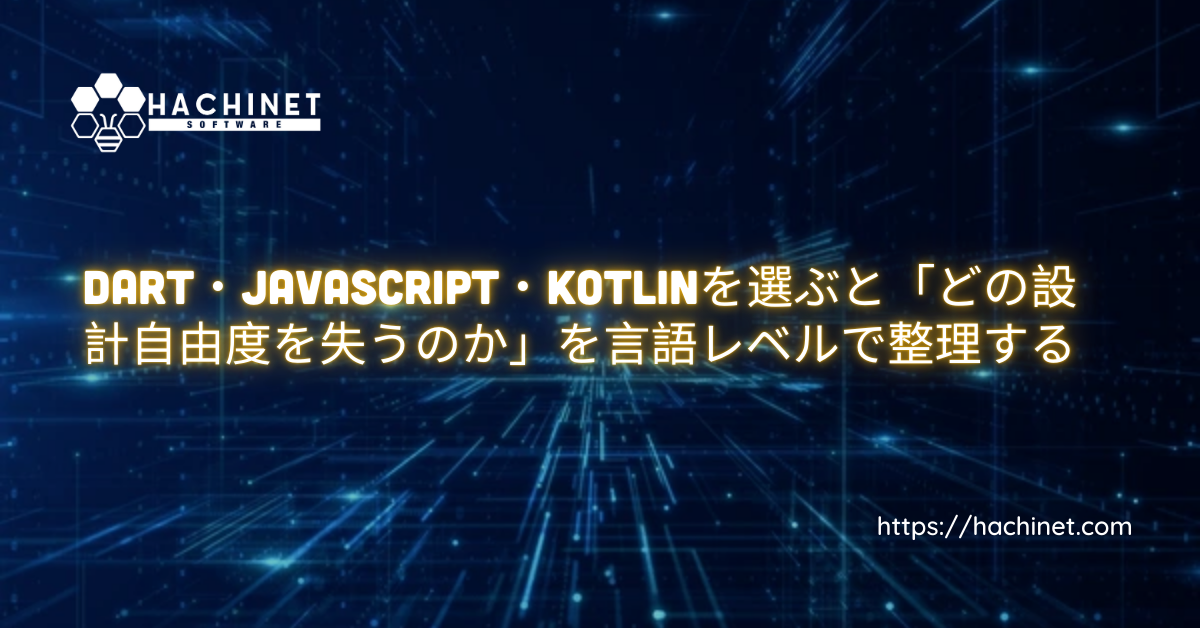
Dart・JavaScript・Kotlinを選ぶと「どの設計自由度を失うのか」を言語レベルで整理する
Dart 入門と検索している時点で、多くの人はまだ「言語」を選んでいるつもりでいます。 しかし実務では、言語選定とは設計の自由度をどこまで手放すかの契約です。 Dart・JavaScript・Kotlinは、用途が違うのではなく、破壊する設計レイヤーが根本的に違う。この記事では、その違いをコードや流行ではなく、アーキテクチャの不可逆点から整理します。

Dartの文法は偶然ではない|基礎構文から読み解く設計思想
Dartは「書けば動く」言語ではありません。代わりに「考えずに書くことを許さない」言語です。本記事では文法を並べるのではなく、Dartがどのような失敗を事前に潰そうとしているのかを軸に解説します。ここを理解すれば、Dartの構文は自然に腑に落ちます。

Dartはなぜ「書かされている感」が強いのか──Flutter・Web・Serverに共通する設計拘束の正体
Web Dart 入門としてDartに触れた多くの人が、「書けるが、自分で設計している感じがしない」という感覚を持ちます。サンプル通りに書けば動く、しかし少し構造を変えた瞬間に全体が崩れる。この現象は学習者の理解不足ではなく、Dartという言語が設計段階で強い制約を内包していることに起因します。本記事では、Dartがどのようにコードの形を縛り、なぜその縛りがFlutter・Web・Serverすべてで同じ問題を引き起こすのかを、実装視点で掘り下げます。
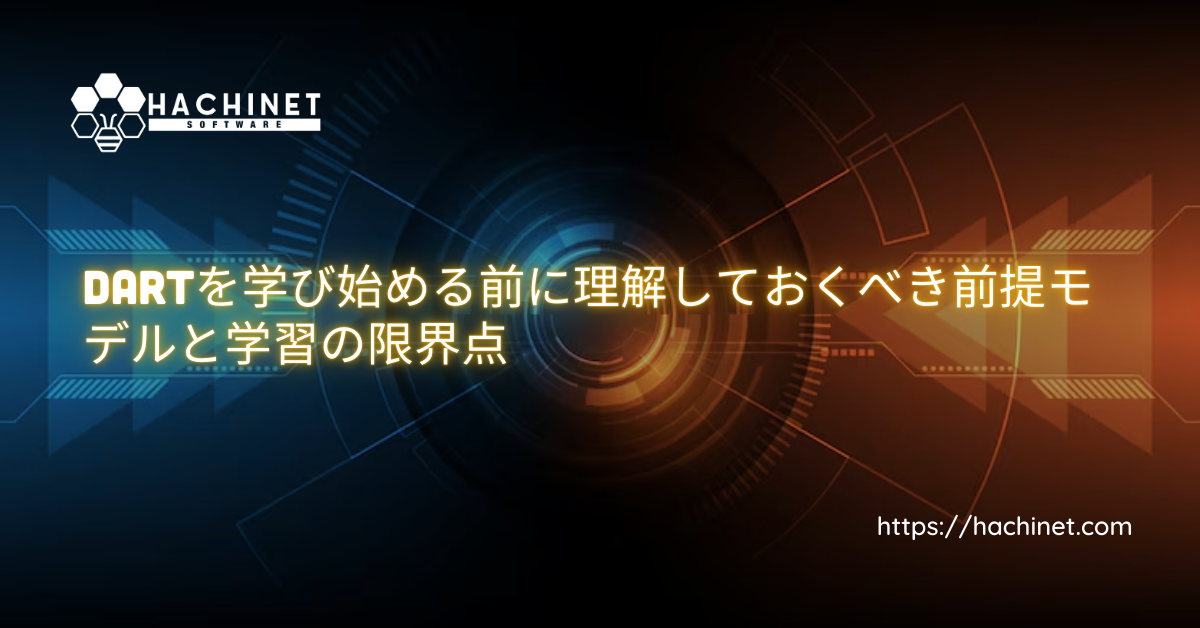
Dartを学び始める前に理解しておくべき前提モデルと学習の限界点
「Dart 入門」という言葉は、Dartが初心者でも気軽に扱える言語であるかのような印象を与えますが、実際のDartは、現代的なアプリケーション開発で前提とされるプログラミングモデルを理解していることを前提に設計された言語です。文法自体は比較的素直であっても、状態管理、非同期処理、型による制約といった考え方を理解しないまま学習を進めると、「動くが理由が分からないコード」が増え、小さな変更で全体が破綻する段階に必ず到達します。本記事では、Dart学習で頻発するつまずきを起点に、学習前にどのレベルの理解が求められるのかを、曖昧な励ましや精神論を排して整理します。
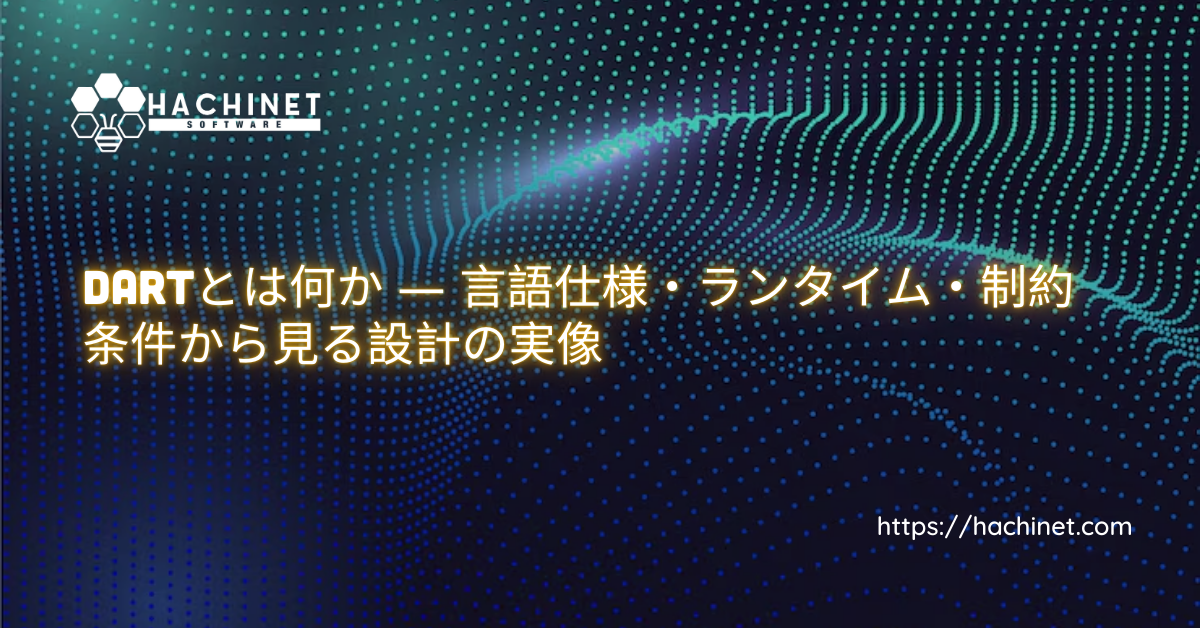
Dartとは何か ― 言語仕様・ランタイム・制約条件から見る設計の実像
Dart 入門や Dartとは というキーワードで語られる内容の多くは、表層的な機能説明に留まっています。しかしDartは、流行に合わせて作られた軽量言語ではなく、明確な制約条件を起点に設計された結果として現在の形に落ち着いた言語です。本記事では、Dartを仕様・ランタイム・設計判断の連鎖として捉え、その必然性を整理します。
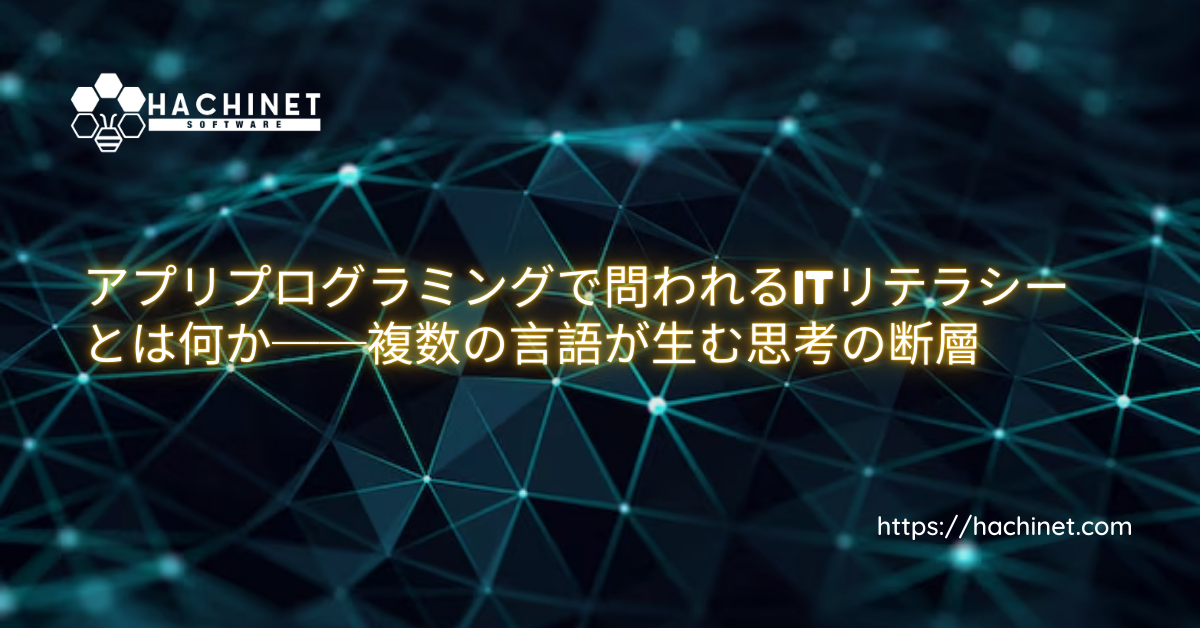
アプリプログラミングで問われるITリテラシーとは何か──複数の言語が生む思考の断層
ITリテラシーがあるかどうかは、プログラミング言語を知っているかでは決まりません。本質は、なぜアプリプログラミングが複数の言語に分かれているのかを、構造として理解しているかです。この記事では、言語ごとに異なる役割と思考モデルを明確にし、非エンジニアが判断を誤る理由を技術構造から説明します。
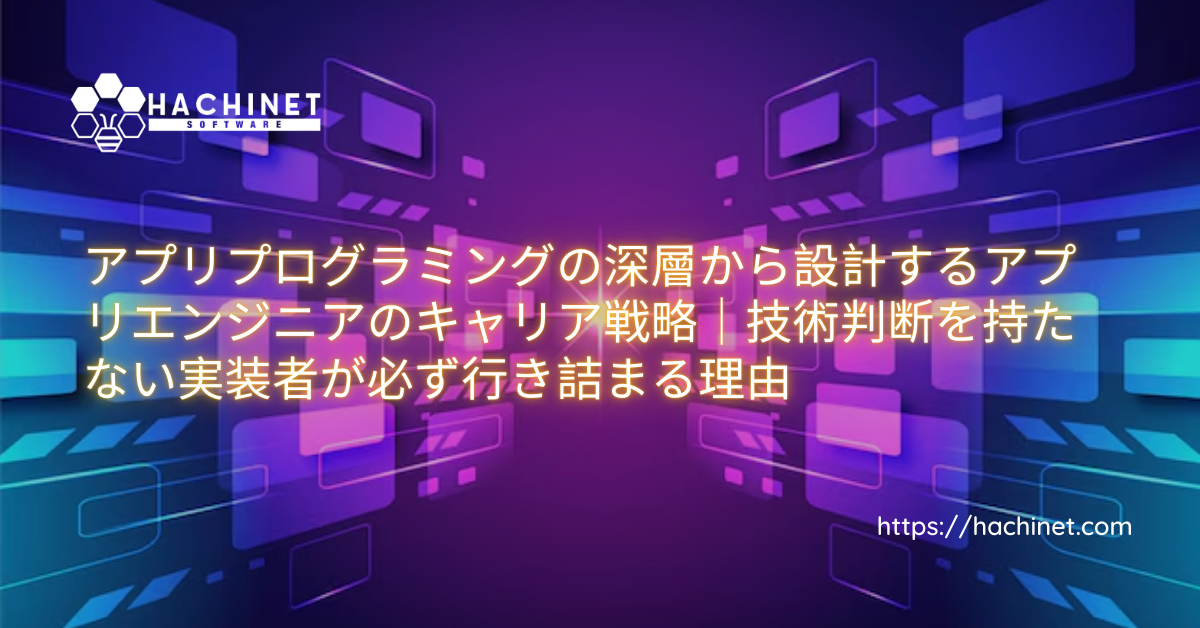
アプリプログラミングの深層から設計するアプリエンジニアのキャリア戦略|技術判断を持たない実装者が必ず行き詰まる理由
アプリプログラミングの経験年数が増えても、技術者としての評価が上がらないケースは珍しくありません。その多くは、アプリ開発を「作る仕事」として捉え続けていることに起因します。アプリエンジニアのキャリア戦略を考えるうえで重要なのは、実装スキルではなく、技術的な判断をどこまで担ってきたかです。本記事では、アプリプログラミングの深層にある設計・判断の観点から、キャリア形成の実態を整理します。
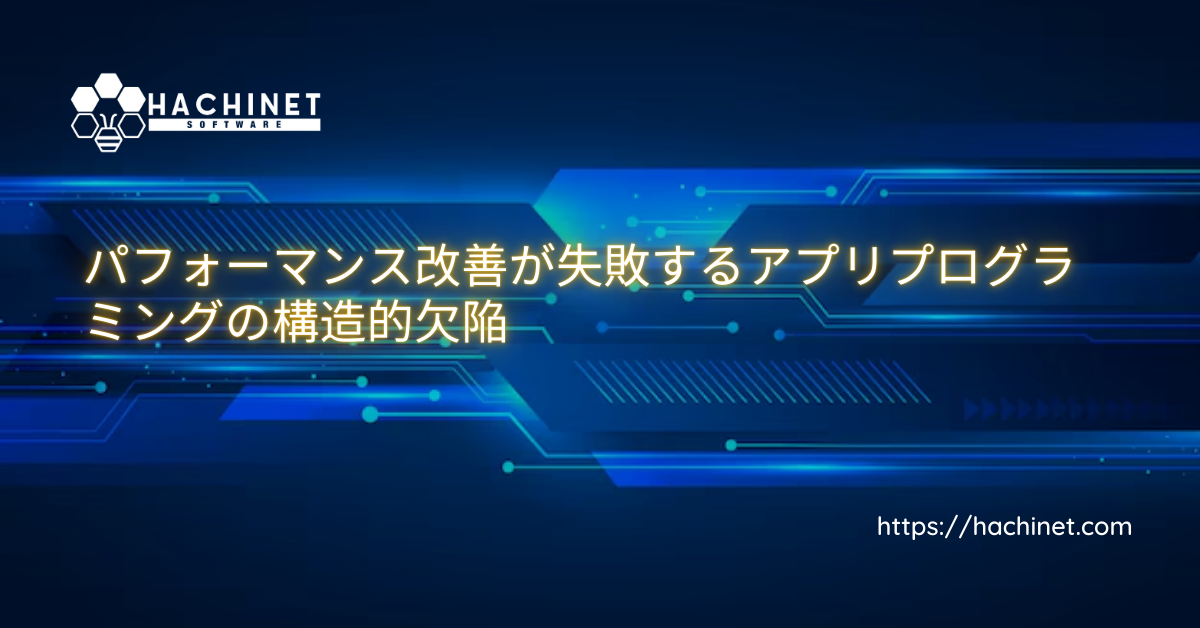
パフォーマンス改善が失敗するアプリプログラミングの構造的欠陥
アプリが重くなるとき、表に出るのはスクロールのカクつきや起動遅延だ。しかしユーザーが離脱する原因は、その「見えている遅さ」ではない。アプリプログラミングの内部で、処理順序・責務分離・実行単位が崩れ始めていることに、誰も気づいていない点にある。
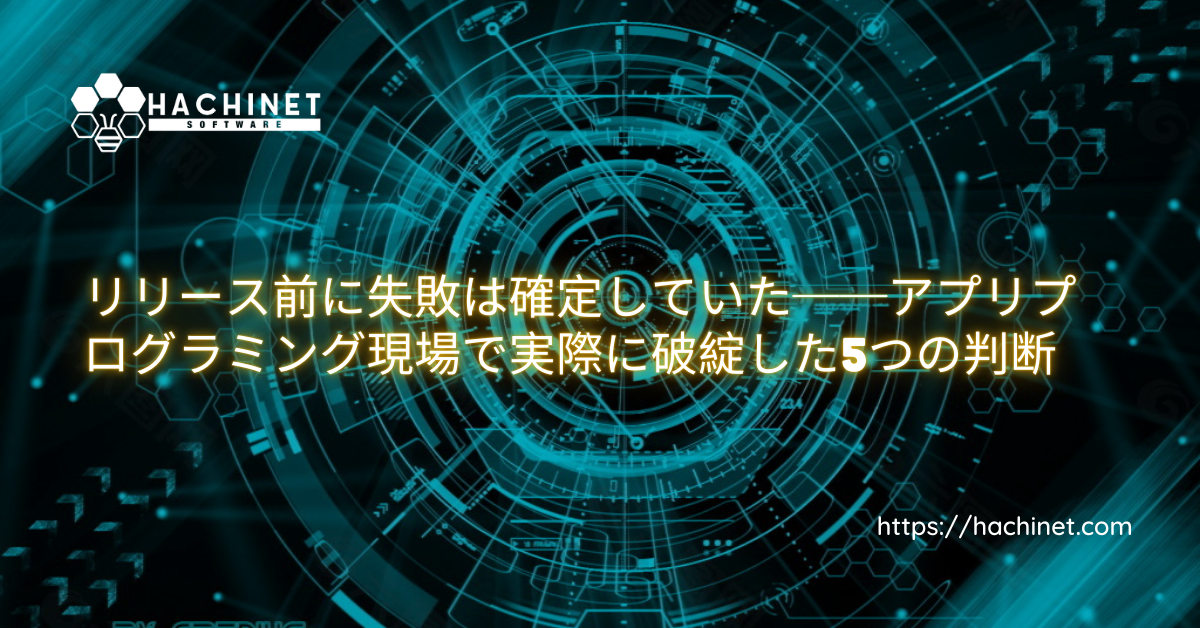
リリース前に失敗は確定していた──アプリプログラミング現場で実際に破綻した5つの判断
アプリプログラミングの失敗は、実装が始まってから起きるものではありません。実際には、設計初期に下した数個の判断によって、後工程の選択肢が静かに消えていきます。本記事では、開発中は一見順調に見えたにもかかわらず、運用段階で破綻した事例をもとに、「どの判断が不可逆だったのか」を構造として整理します。



