なぜ日本企業のSaaS化は進まないのか?現場文化とレガシーが生む本当の壁
近年、クラウド化やDX(デジタルトランスフォーメーション)が加速する中で、SaaSの導入は企業の生産性を高める有効な手段として注目されています。しかし、日本企業では欧米に比べSaaS化が思うように進まず、「なぜ日本だけ遅れているのか」という議論が続いています。その背景には、単なる技術格差ではなく、長年にわたるレガシーシステムへの依存、稟議や合意形成を重んじる企業文化、そして“現場の声が経営に届きにくい”という構造的課題があります。本記事では、現場のリアルな視点を交えながら、日本企業のSaaS化が進まない理由と、それを乗り越えるための具体的な突破口を探っていきます。
2025年10月31日
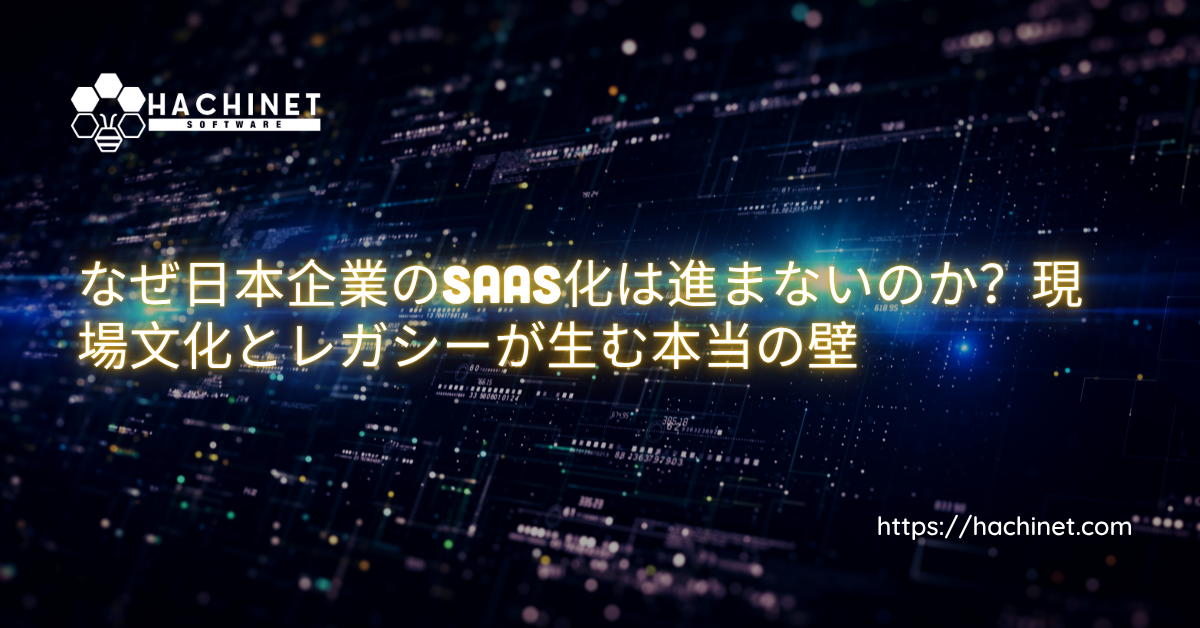
近年、クラウド化やDX(デジタルトランスフォーメーション)が加速する中で、SaaSの導入は企業の生産性を高める有効な手段として注目されています。しかし、日本企業では欧米に比べSaaS化が思うように進まず、「なぜ日本だけ遅れているのか」という議論が続いています。その背景には、単なる技術格差ではなく、長年にわたるレガシーシステムへの依存、稟議や合意形成を重んじる企業文化、そして“現場の声が経営に届きにくい”という構造的課題があります。本記事では、現場のリアルな視点を交えながら、日本企業のSaaS化が進まない理由と、それを乗り越えるための具体的な突破口を探っていきます。
1. レガシーシステムと“2025年の崖”としての構造的壁
最大の障壁は、長年運用されてきた基幹系・業務系のレガシーシステムです。カスタマイズを重ねたオンプレミス環境がブラックボックス化し、保守コストが高騰。「変えると業務が止まるのでは」という不安から、新しいSaaSへの移行をためらう企業が多く見られます。
また、日本企業では「現場力」や属人的ノウハウが強みとされてきたため、システム刷新よりも既存運用を守る文化が根づいています。このような技術的・心理的なレガシー構造が、SaaS導入の“第一歩”を阻んでいます。
2. 社内文化・意思決定プロセスの壁
文化面でも課題があります。日本企業では稟議・合意形成に時間がかかり、変化よりも現状維持が優先されがちです。現場が必要性を感じていても、承認や調整に時間がかかり、導入が遅れます。
さらに「SaaSは自社業務に合わない」「カスタマイズしないと使えない」といった先入観も根強く、標準化を受け入れにくい傾向があります。
導入しても効果を実感できず、「なぜ業務が楽にならないのか」と現場に不満が生まれるケースもあります。このように、社内文化と意思決定のプロセスがSaaSの「検討」から「定着」への移行を妨げています。
3. 現場のITリテラシー・使いこなしの差とSaaSスプロール

現場のリテラシーや運用体制も課題です。多くの企業では「導入はしたが定着しない」という声が上がっています。UI/UXが業務フローに合わなかったり、教育不足により操作が定着しない、あるいは既存のExcel・紙運用が残るなど、結果的に手間が増えるケースもあります。
また、部署ごとに異なるSaaSを導入する「SaaSスプロール」が発生し、全体管理が困難に。この混乱が次の導入判断を慎重にさせる悪循環を生んでいます。SaaS導入は“ゴール”ではなく、「使われ、定着する」までを見据える必要があります。
4. 解決策:現場と経営がつながるSaaS化へのステップ
これらの課題を乗り越えるには、次の4つのステップが有効です。
・現場ニーズの可視化と小規模パイロット
現場の困りごとを丁寧にヒアリングし、まずは小規模な導入で成果を可視化。成功事例を横展開して社内理解を得る。
・レガシーシステムの棚卸しと“つなぐ/置き換える”戦略
既存システムを整理・文書化し、どこをSaaSと連携させるか、どこを置き換えるかを明確にする。
・現場参加型の設計と教育
現場担当者を導入段階から巻き込み、テストや操作教育を実施。定期的な改善会議を通じて定着を図る。
・経営層との対話とKPI設定
SaaS化による効果を数値化し、経営層に共有。情報共有や意思決定スピードの改善を示すことで理解を深める。
日本企業のSaaS化が進まない要因は、単に技術やリソースの不足ではなく、長年培われてきた文化と構造の中にあります。レガシーシステムを守り続ける安心志向、慎重な意思決定プロセス、そして現場の改善意識と経営戦略のギャップ——これらを乗り越えるには、現場主導の小さな実験から成果を示し、組織全体の認識を変えていくことが欠かせません。「変わらない日本企業」というイメージを脱し、SaaSを“使いこなす文化”を根づかせることこそ、これからの競争力を左右する鍵となるでしょう。
- オフショア開発
- エンジニア人材派遣
- ラボ開発
- ソフトウェアテスト
電話番号: (+84)2462 900 388
メール: contact@hachinet.com
お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。
無料見積もりはこちらから
Tags
ご質問がある場合、またはハチネットに協力する場合
こちらに情報を残してください。折り返しご連絡いたします。
関連記事

Dartは本当に就職に強いのか?Flutter求人の構造・年収帯・生存戦略まで踏み込んで解説
Dart入門と検索する段階で、多くの人はすでに疑問を持っています。「学びやすいらしいが、それで就職できるのか」。結論を先に言えば、Dartは単体では市場価値を持ちません。評価対象はあくまで Flutter です。本記事では、日本・ベトナム・欧米市場の採用構造を具体的に分解し、年収レンジ感やスキル要件まで踏み込んで現実的に整理します。

Flutterで頭打ちになる人が見落としているDart基礎設計の決定的差
Flutterは学習初期の成功体験が早い技術です。しかし半年後、コードが肥大化し、再利用できず、状態管理が複雑になり、自分でも触りたくないプロジェクトになるケースは少なくありません。その分岐点はDart理解の深さです。Dart 入門レベルの文法理解で止まり、言語仕様や実行モデルに踏み込まなかった人ほど設計が破綻します。本記事では「なぜDart理解が不足するとFlutter開発が不安定になるのか」を技術構造レベルで解説します。

Dartのオブジェクト指向は「設計しない」ことで成立している
Dartのオブジェクト指向は、学習段階では拍子抜けするほど単純です。しかし実務で数万行規模になると、多くの言語で起きる「設計崩壊」が、Dartでは驚くほど起きにくい。本記事では、その理由を「美しい設計論」ではなく、どこで壊れ、どこで踏みとどまるのかという実装結果ベースで掘り下げます。
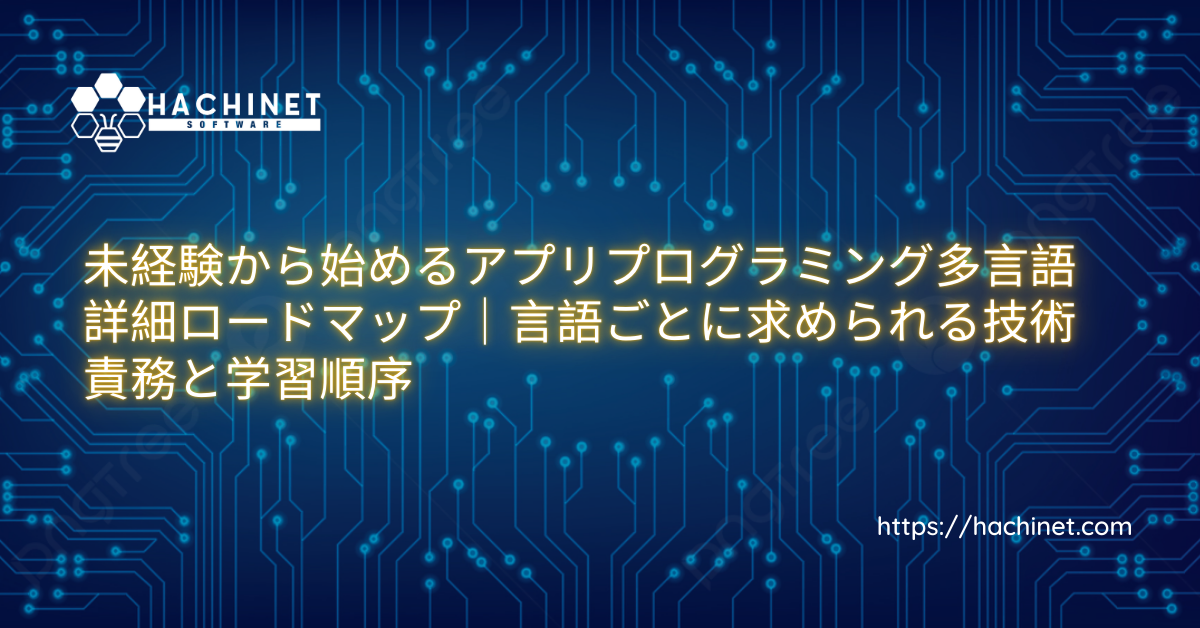
未経験から始めるアプリプログラミング多言語詳細ロードマップ|言語ごとに求められる技術責務と学習順序
未経験からアプリプログラミングを学ぶ際、多くの人は「どの言語を覚えればアプリが作れるか」という問いを立てます。しかし実務では、アプリは単一言語で完結することはなく、複数の言語が異なる責務を分担する構造体として存在します。本記事では、言語を単なるスキルではなく、アプリを成立させるための必須構成要素として整理します。
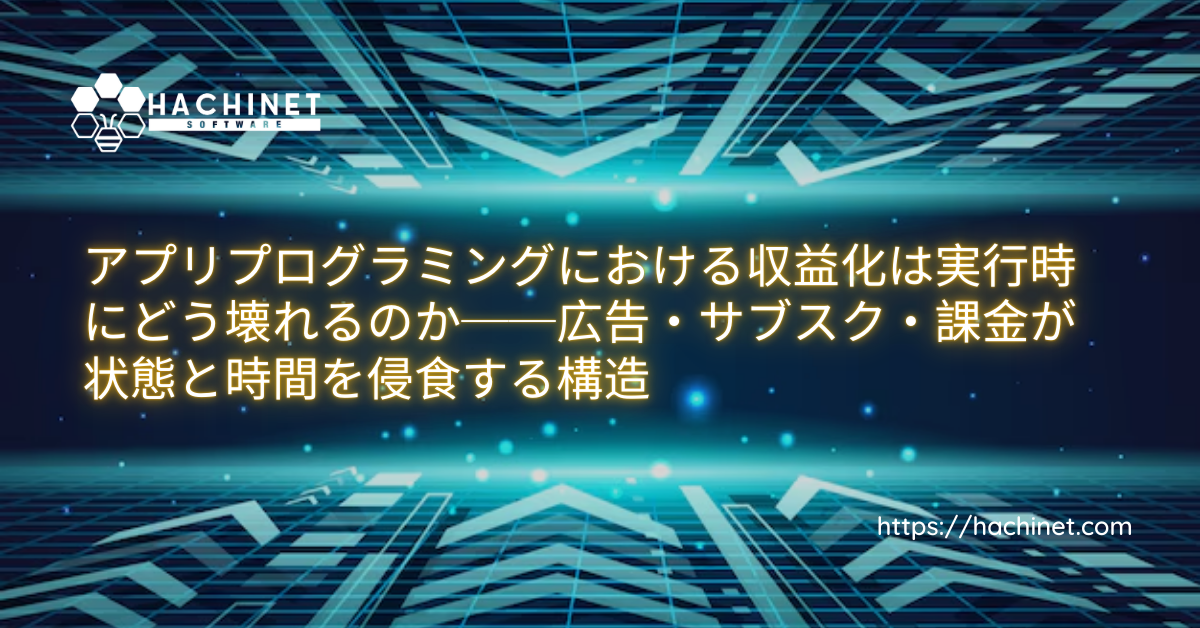
アプリプログラミングにおける収益化は実行時にどう壊れるのか──広告・サブスク・課金が状態と時間を侵食する構造
アプリプログラミングにおいて、収益化を組み込むという行為は「機能を増やす」ことではない。実行時の状態数を爆発的に増やし、時間軸を複数に分岐させる行為だ。この変化を設計で制御できなかった瞬間から、アプリは静かに壊れ始める。

MVPは試作品ではない──スタートアップのアプリプログラミングで最初に固定される3つの技術前提
スタートアップが最初に作るアプリを「MVPだから雑でいい」と考えると、ほぼ確実に作り直しになります。理由は単純で、アプリプログラミングではMVPであっても必ず固定されてしまう技術前提が存在するからです。本記事では、初期アプリで何を作るかではなく、何が不可逆に決まってしまうのかを、実装レベルで整理します。



