組み込みプログラミングとは? なぜ組み込みプログラミングはそれほどホットなの?
組み込みプログラミングは、特定の環境または親システムに組み込まれている自律システムのプログラミング用語である。 これらは、ハードウェアとソフトウェアの両方を統合するシステムである。
2020年09月11日

組み込みプログラミングは、特定の環境または親システムに組み込まれている自律システムのプログラミング用語である。 これらは、ハードウェアとソフトウェアの両方を統合するシステムである。
1.組み込みプログラミングとは?
組み込みプログラミングは、特定の環境または親システムに組み込まれている自律システムのプログラミング用語である。 これらは、ハードウェアとソフトウェアの両方を統合するシステムである。
主な目的は、産業、制御自動化、および通信の多くの分野における特殊な問題に対応することである。 多くの場合、組み込みシステムは特定の特殊な機能を実行するように設計されている。
このプログラミングは特定のタスクのためにのみ構築されているため、作成者はそれを最適化してサイズとコストを最小限に抑えることができる。 組み込みシステムは非常に多様で種類が豊富である。
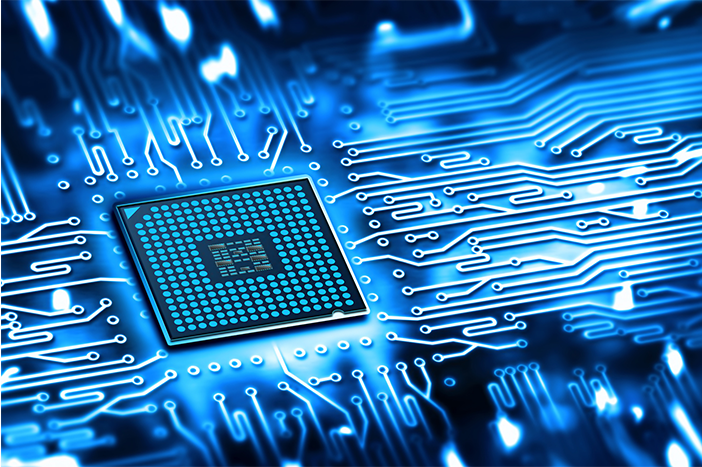
組み込みシステムの基本コンポーネント
- ROM:プログラム、固定データ、または定数データが含まれている。 現在、ほとんどのシステムは、ROMを置き換えるためにEEPROMまたはFLASHを使用している。これは、新しいプログラムの書き込み、削除、および更新ができるためです。
- RAM:実行可能プログラムと一時変数を格納する。
- MCU:中央計算プロセッサ。
- ADC、DAC、通信ユニットUART、I2Cなどのペリフェラルもある。
2.組み込みプログラグミアプリケケシオン
- コンピュータ、エレクトロニクス、銀行、電気通信業界などでは組み込みシステムが広く使用されている 。
- 組み込みシステムは、ソフトウェアとハードウェアの両方に統合されており、マイクロプロセッサなどのプログラミングデバイスに統合されている。
- 組み込みシステムとPC、ハンドヘルドPDAデバイスは、システムの品質を高めてコストを削減するために特定の機能を特化する設計のために異なる。
3.いくつかの比較および組み込みプログラミングツール
- クロスToolChians(Linux):AT91SAMコンパイラーはLinux環境で実行される。
- Keil(Windows):ARMシリーズ用のWindows環境プログラミング(STM32F4xxなど)での実行。
- Putty.exe(Windows):Ethernetまたは2つのRS232標準を介してSecure Shellにアクセスするプログラミングをサポートするプログラム

4.組み込みプログラミングは後で何をするか?
組み込みプログラミングは非常に広い業界であり、理解しやすくしているが、組み込みプログラミングは次のように2つの方向に分けることができる。
Embedded software
あなたは真の開発者であり、優れたプログラマーに成長することができ、あなたはチームと一緒に組み込み製品用のソフトウェア製品を開発するでしょう。 これは、アプリケーション(Web、デスクトップ、またはモバイルアプリ)、ファームウェア、OS(オペレーティングシステム)、ドライバーなどである。
あなたの仕事は、コードの記述、コードのテスト、製品の要件とドキュメントの記述である。
Embedded hardware
あなたは、PCBデザイン、テストボードとも呼ばれるボードデザイナーになる。 この仕事をするには、ハードウェアと電子機器に非常に優れている必要がある。
会社に参加する各プロジェクトには、特定のプロセスがあり、タスクを受け取って完了する前に、そのプロセスを理解する必要がある。 しかし、安心してください、あなたは間違いなく仕事を成し遂げるでしょう。
5.組み込みプログラミングエンジニアになるために必要な知識
5.1必要な基礎知識
- Cプログラミングを学ぶ:Cをエキスパートレベルまで学習する必要がある。これは組み込みプログラミングで最も重要な言語である。
- 英語:少なくとも技術資料、特にデータシートを読むことができるはずである。
- 電子的知識:ロジック、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサー、ADC、タイマー、割り込みなどの知識。
- 通信タイプ(プロトコル):UART、I2C、SPI、RS232、JTAGなど(詳細:SATA、PCIE、USB、CAN、MOST)。
- オペレーティングシステム:オペレーティングシステムアーキテクチャ、コンピューターアーキテクチャ、特にLinuxオペレーティングシステム。
- データ構造とアルゴリズム:ハードウェアの専門家として、コーディングも必要です。コーディングした場合は、アルゴリズムも必要である。
- メモリ:NOR、NAND、SRAM、DRAMなど。
- リアルタイムOS。

5.2専門知識
Embedded software
- アプリケーションプログラミング:C ++、Java。
- プログラムデバイスドライバー(C言語を使用。
- Androidプログラミング、Web(基本)プログラミング。
- スクリプト:Perl、Python、特にLinux上のシェルスクリプト。
- 非常に優れたデータ構造とアルゴリズム。
- ビルド環境:Makefile、Cmake。
Embedded hardware
- PCBデザイン:AllegroまたはAntium。
- 回路図の設計:これを行うには、優れた電子知識が必要である。
- テストボード:設計後、テストボードを知る必要がある。
- 最適なプロジェクトのコンポーネントを確認、評価、選択する。
- ゲージツールを使用する。
- 回路のはんだ付け、回路の固定(フリーランサーの場合 )。
※以下通り弊社の連絡先
電話番号: (+84)2462 900 388
メール: konnichiwa@hachinet.jp
お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。
- オフショア開発
- エンジニア人材派遣
- ラボ開発
- ソフトウェアテスト
電話番号: (+84)2462 900 388
メール: contact@hachinet.com
お電話でのご相談/お申し込み等、お気軽にご連絡くださいませ。
無料見積もりはこちらから
Tags
ご質問がある場合、またはハチネットに協力する場合
こちらに情報を残してください。折り返しご連絡いたします。
関連記事

Dartは本当に就職に強いのか?Flutter求人の構造・年収帯・生存戦略まで踏み込んで解説
Dart入門と検索する段階で、多くの人はすでに疑問を持っています。「学びやすいらしいが、それで就職できるのか」。結論を先に言えば、Dartは単体では市場価値を持ちません。評価対象はあくまで Flutter です。本記事では、日本・ベトナム・欧米市場の採用構造を具体的に分解し、年収レンジ感やスキル要件まで踏み込んで現実的に整理します。

Flutterで頭打ちになる人が見落としているDart基礎設計の決定的差
Flutterは学習初期の成功体験が早い技術です。しかし半年後、コードが肥大化し、再利用できず、状態管理が複雑になり、自分でも触りたくないプロジェクトになるケースは少なくありません。その分岐点はDart理解の深さです。Dart 入門レベルの文法理解で止まり、言語仕様や実行モデルに踏み込まなかった人ほど設計が破綻します。本記事では「なぜDart理解が不足するとFlutter開発が不安定になるのか」を技術構造レベルで解説します。

Dartのオブジェクト指向は「設計しない」ことで成立している
Dartのオブジェクト指向は、学習段階では拍子抜けするほど単純です。しかし実務で数万行規模になると、多くの言語で起きる「設計崩壊」が、Dartでは驚くほど起きにくい。本記事では、その理由を「美しい設計論」ではなく、どこで壊れ、どこで踏みとどまるのかという実装結果ベースで掘り下げます。
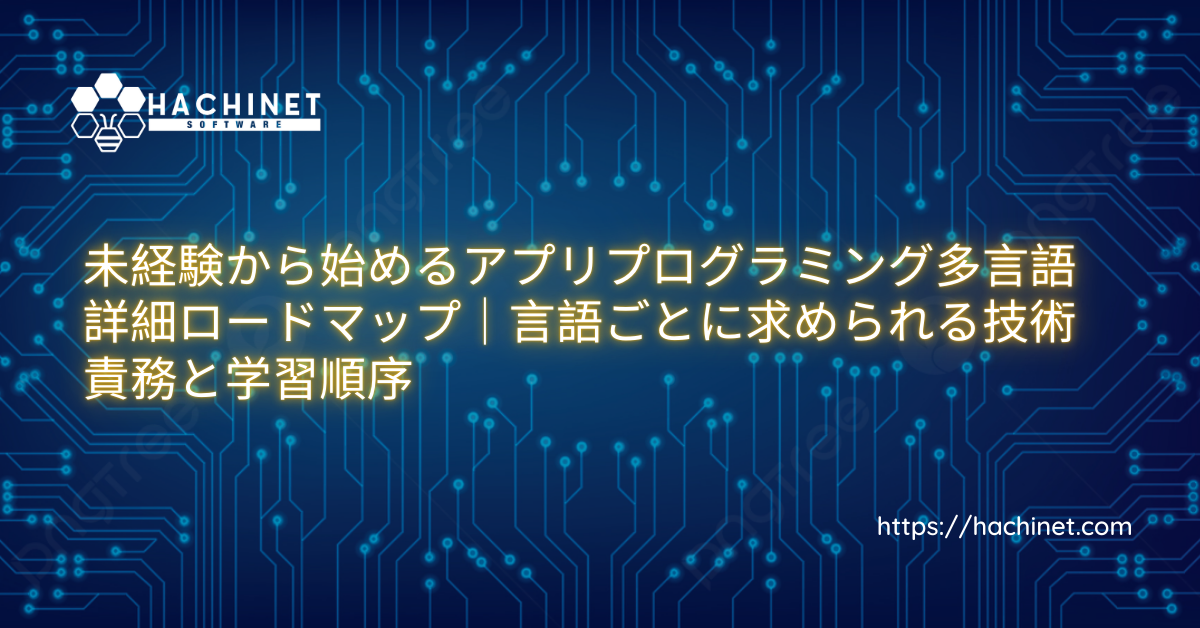
未経験から始めるアプリプログラミング多言語詳細ロードマップ|言語ごとに求められる技術責務と学習順序
未経験からアプリプログラミングを学ぶ際、多くの人は「どの言語を覚えればアプリが作れるか」という問いを立てます。しかし実務では、アプリは単一言語で完結することはなく、複数の言語が異なる責務を分担する構造体として存在します。本記事では、言語を単なるスキルではなく、アプリを成立させるための必須構成要素として整理します。
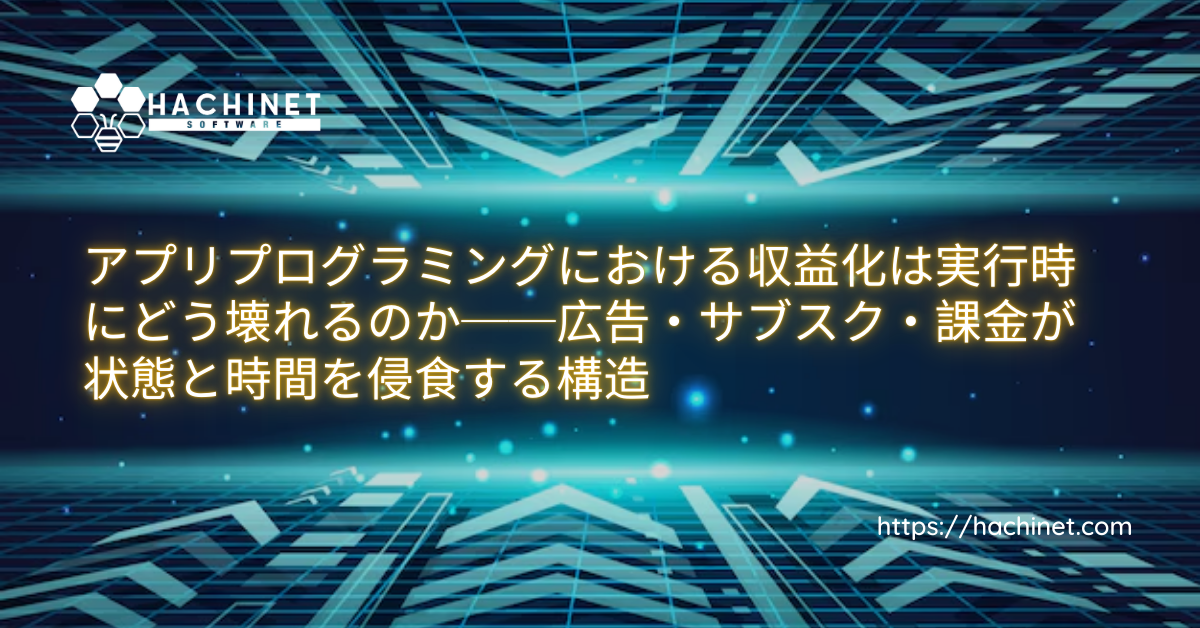
アプリプログラミングにおける収益化は実行時にどう壊れるのか──広告・サブスク・課金が状態と時間を侵食する構造
アプリプログラミングにおいて、収益化を組み込むという行為は「機能を増やす」ことではない。実行時の状態数を爆発的に増やし、時間軸を複数に分岐させる行為だ。この変化を設計で制御できなかった瞬間から、アプリは静かに壊れ始める。

MVPは試作品ではない──スタートアップのアプリプログラミングで最初に固定される3つの技術前提
スタートアップが最初に作るアプリを「MVPだから雑でいい」と考えると、ほぼ確実に作り直しになります。理由は単純で、アプリプログラミングではMVPであっても必ず固定されてしまう技術前提が存在するからです。本記事では、初期アプリで何を作るかではなく、何が不可逆に決まってしまうのかを、実装レベルで整理します。



